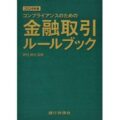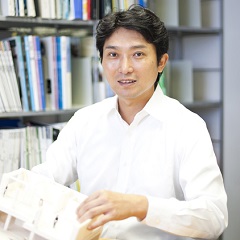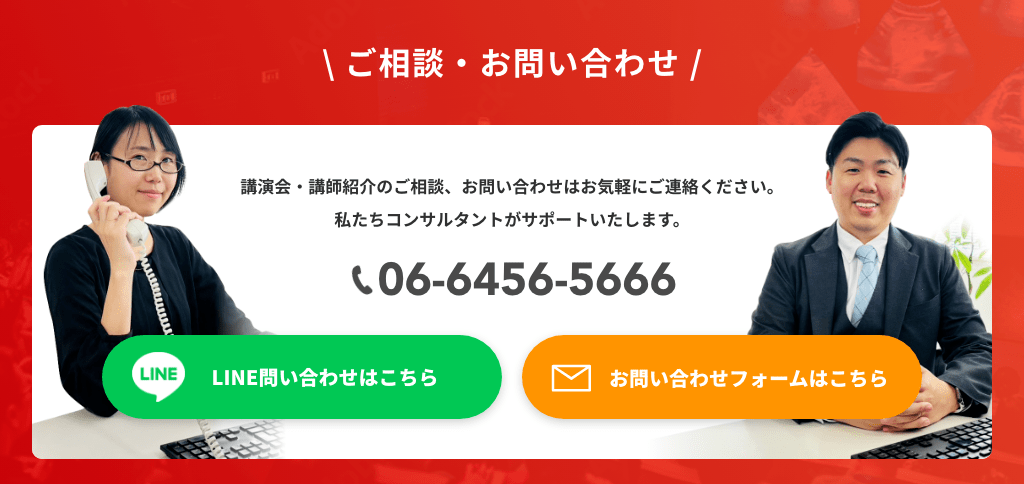のむら しゅうや野村 修也
- 肩書き
- 弁護士
中央大学法科大学院教授 - 出身・ゆかりの地
- 北海道
プロフィール
1981年 私立函館ラ・サール高等学校卒業
1985年 中央大学法学部卒業
1987年 中央大学大学院法学研究科博士前期課程修了、2年後、後期課程中退
2004年 弁護士登録
2015年度 「企業が選ぶ弁護士ランキング」ガバナンス部門で第8位!
2024年 内閣府本府参与(再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース)の調査
2024年 函館市政策アドバイザー(~2026年)
「商法」「会社法」「金融法」が専門で、なかでも「コーポレート・ガバナンス」「コンプライアンス」「規制改革」の研究で知られる。M&Aなど企業法務の第一線で活躍する弁護士でもあり、日経新聞による「企業が選ぶ弁護士ランキング」では、去年・今年と2年連続でベストテン入りしている。
法制審議会や金融審議会等を通じて各種の立法に関与。1998年に金融監督庁が発足した際には、初の民間官僚として参事に就任し、その後、金融庁顧問、総務省顧問、郵政民営化委員、東京都参与、司法試験考査委員、法制審議会委員などを歴任した。いわゆる「消えた年金」「宙に浮いた年金」等の年金記録問題では検証委員に就任。その後、内閣総理大臣の特命を受け「年金記録問題特別チーム」の室長として問題の解明にあたった。2010年発足の(公財)日本生産性本部「わたしたち生活者のための「共通番号」推進協議会」では幹事を務め、2011年には国会の「東京電力福島原子力発電所事故調査委員会」の主査として報告書をとりまとめた。
各省庁での活動は政策立案や調査研究にとどまらず、法令等遵守調査室長として公務員のコンプライアンスを監視する等活動は幅広く多岐にわたる。
近年は、報道テレビ番組のコメンテーターとして活躍。テレビドラマの監修をつとめた経験もある。
現在の公職としては大臣任用の厚生労働省顧問を務める。
中央大学では、伝統ある陸上部の部長として、選手を率いて世界陸上や箱根駅伝に参戦中。
主な講演実績
中央大学附属高校/日本経団連/日弁連/日本公認会計士協会/日本司法書士会/損害保険事業総合研究所/損害保険代理店業協会/日本青年会議所/株式会社TKC/日本生産性本部/日本いいね!プロジェクト/有斐閣/株式会社ディーバ/公益財団法人資本市場研究会 他多数
主なメディア出演
テレビ朝日「報道ステーション」「サンデーLIVE‼︎」
読売テレビ「情報ライブ ミヤネ屋」「かんさい情報ネットten」
中京テレビ「キャッチ!」他
主な講演のテーマ
1. コーポレート・ガバナンス改革 ~最近の他業界の事例を踏まえて~
政府は「攻めのコーポレート・ガバナンス」に向けた改革を矢継ぎ早に打ち出しています。ハード・ローとしては会社法が改正され、ソフト・ローとしては機関投資家向けのスチュワードシップ・コードと上場会社等向けのコーポレートガバナンス・コードが制度化されました。はたしてこの施策が、海外に比べ見劣りするROE(自己資本利益率)の改善につながるのか、海外投資家からも熱い視線が向けられています。
他方で、コーポレート・ガバナンスの優等生と言われてきた企業において、大規模な不適切会計が発覚し、上場企業に対する世間の目は厳しさを増しています。社外取締役を重視した委員会型の会社組織であっても、こうした事態が生ずることを踏まえ、改めてコーポレート・ガバナンスの本質を考えることが必要になっています。
そこで、本講演では会社法の理論と実務に精通し不祥事調査にも多く携わっている講師がこうした2つの観点から最近の他業界の具 体的な事例をもとに近時のコーポレート・ガバナンス改革を分析し、その課題を解説します。理論的な問題だけではなく、例えば監査等委員会設置会社への移行を検討されている会社関係者の方にもお役に立てるような、実践的な論点も網羅的に取り上げます。
コンプライアンス、検査・監査部門の皆様を始めとして総務・経営企画等より多数の方々のご参加をお待ちしております。
2. 企業の社会的責任~コンプライアンスの神髄~
コンプライアンスとは、法令遵守と理解されることが多くありますが、ただ法律を守るということではなく、社会からの要請に応え、企業価値を守るための「リスク管理」です。重要なのは、法律を守ったという過去の結果では無く、組織・企業での体制づくりの中で、これからのリスクが管理されていること。これまでに不祥事を起こしてしまった企業事例をもとに解説します。
3. 人工知能(AI)によって私たちの暮らしはどう変わるのか~金融・教育・ビジネスの未来~
人工知能(AI)の発展により、昨今では金融・教育・仕事・子育てと生活のあらゆるところで変化が起こりはじめ、
社会の仕組みやルールも大幅な見直しを迫られるようになりました。
私達は今、何を考え、何を学んでおくべきなのでしょうか-。
未来の暮らしに向けて、皆様と共に考えてみたいと思います。
4. 会社法改正と今後の企業ガバナンス
5. 実例から学ぶM&Aの基礎知識
6. 知的財産を活かした会社経営
7. これだけは知っておきたいマイナンバー制度