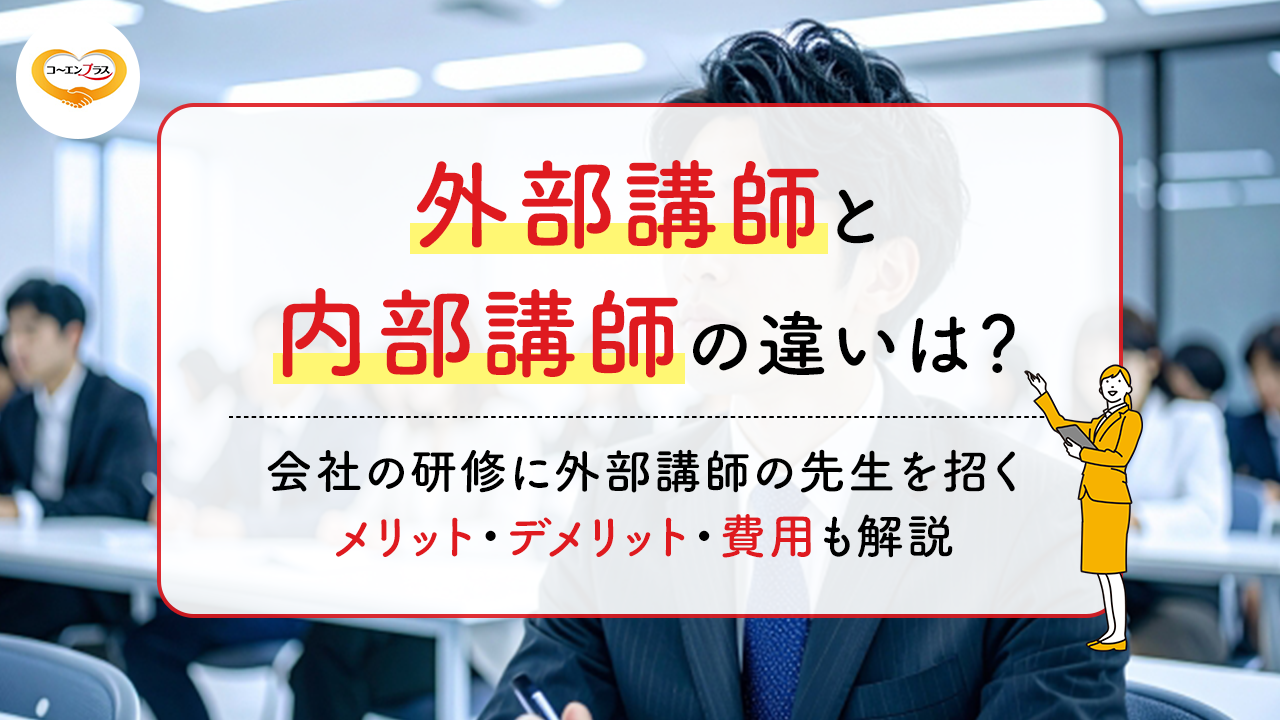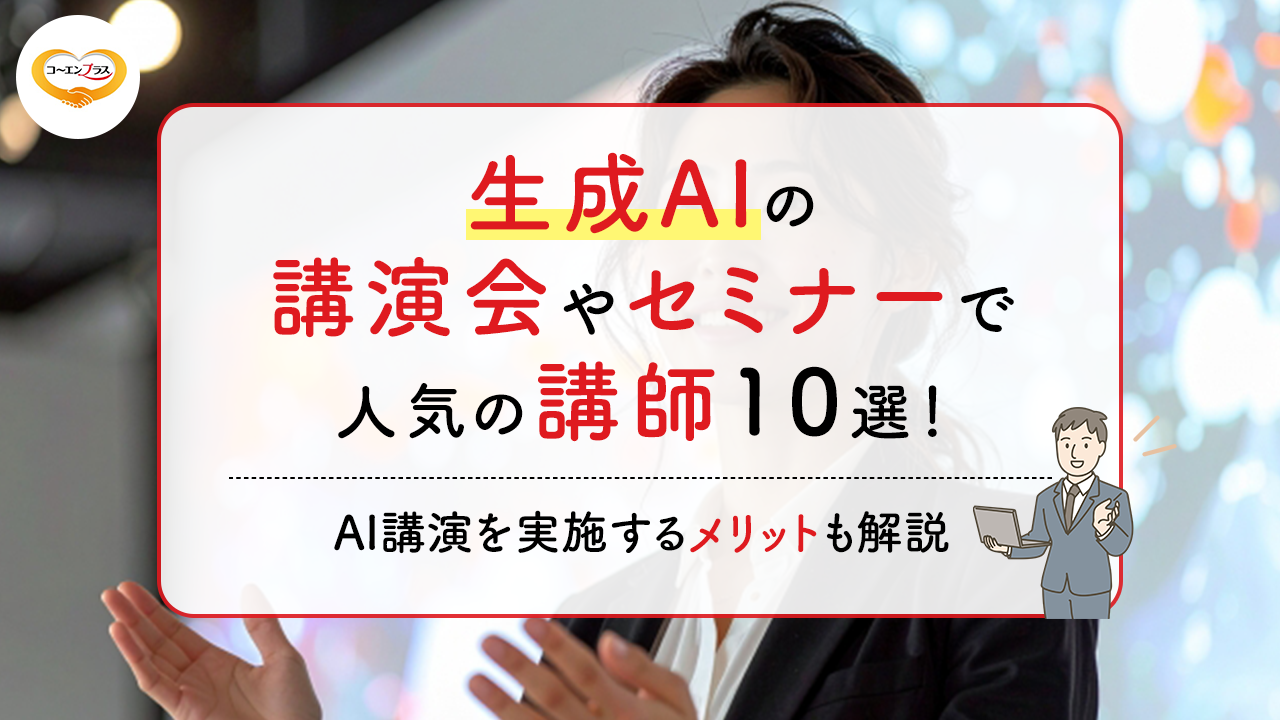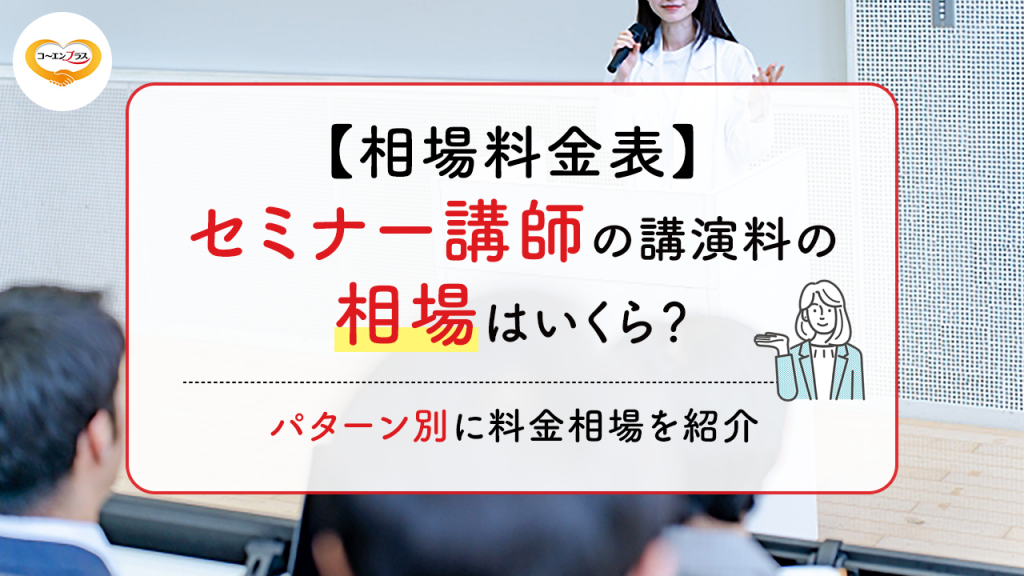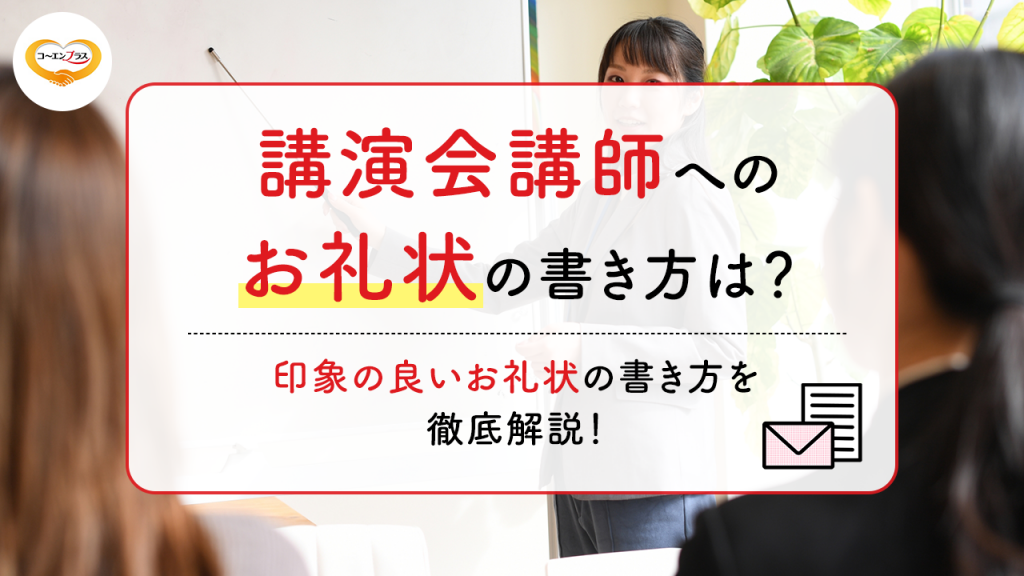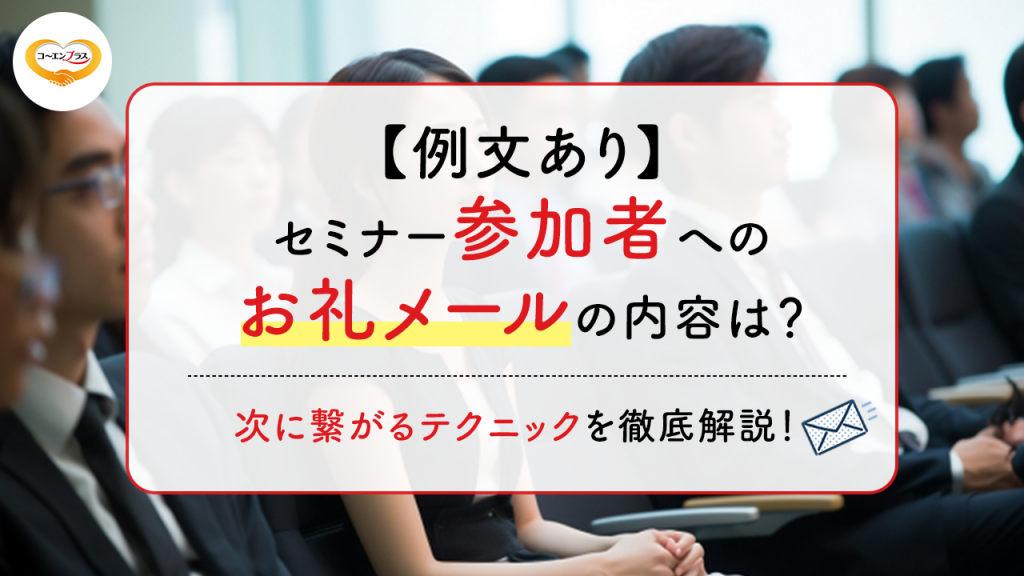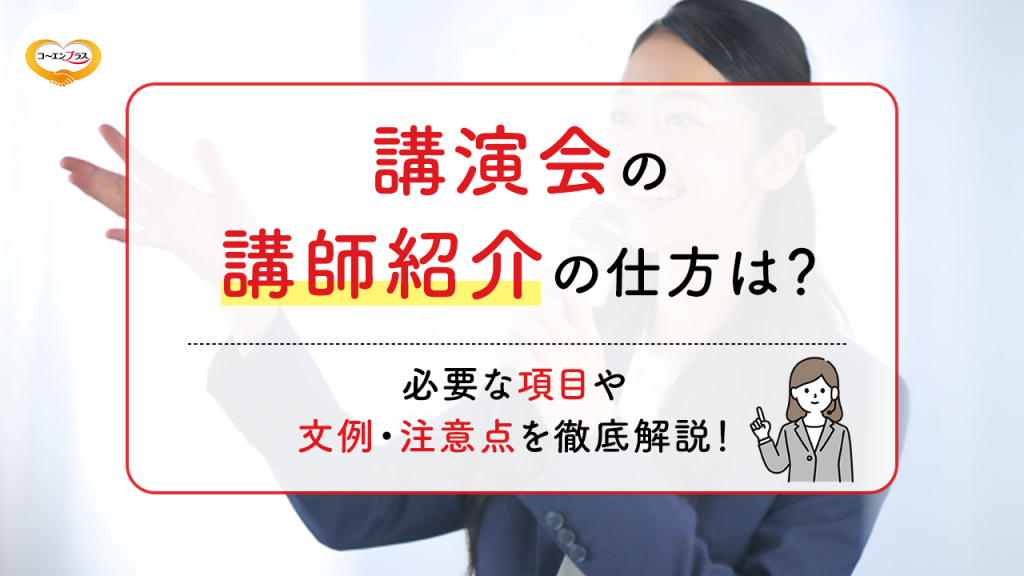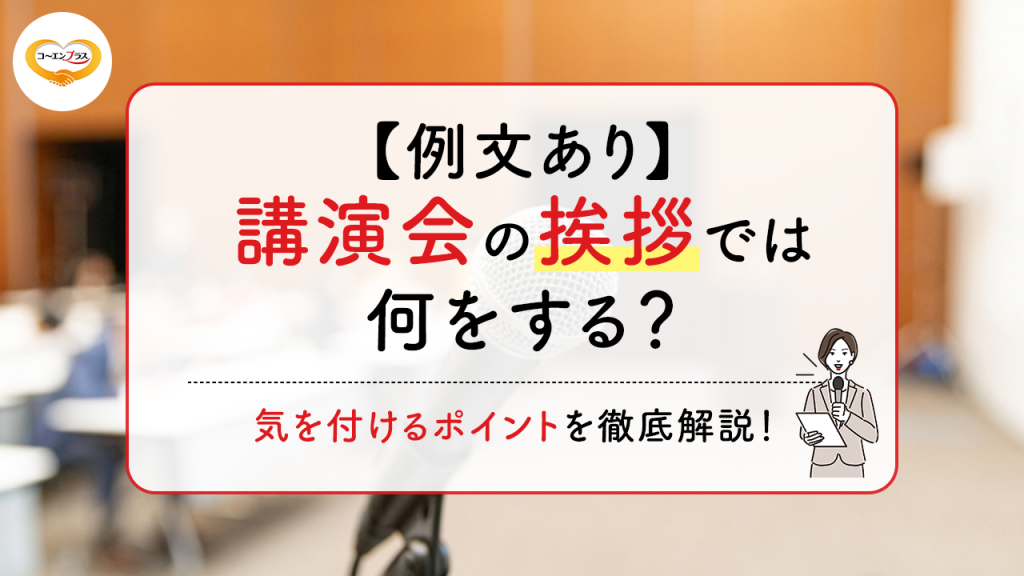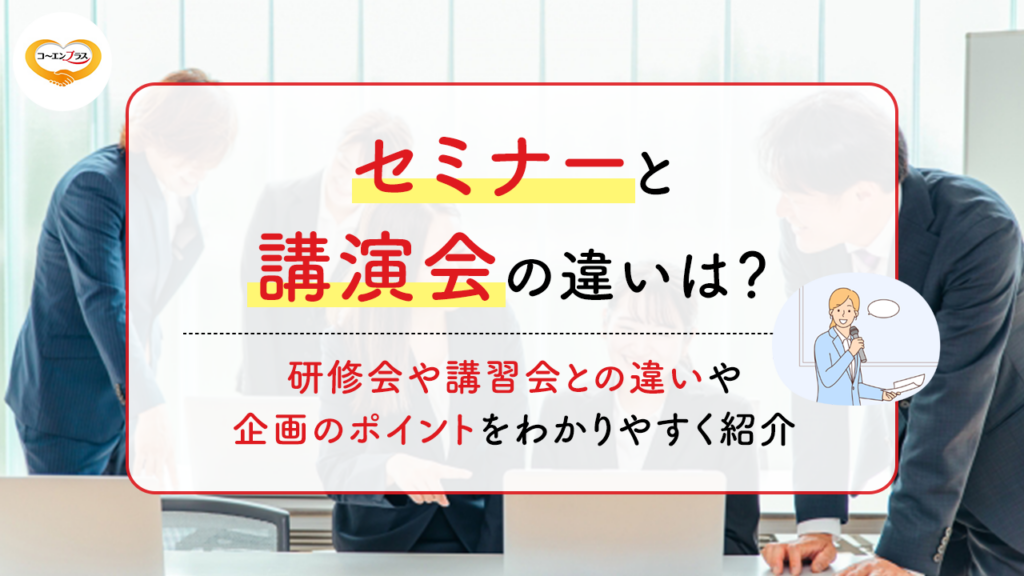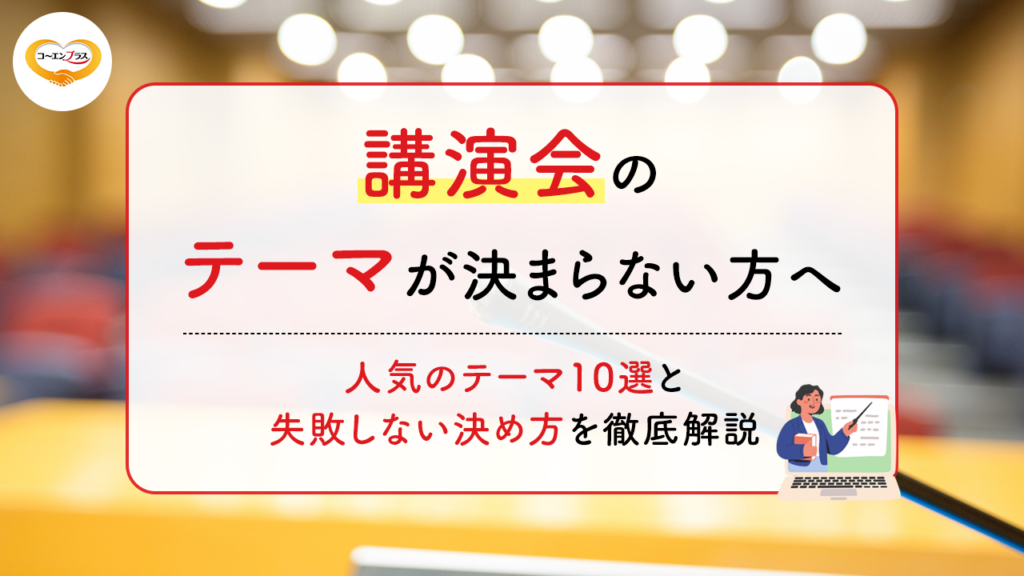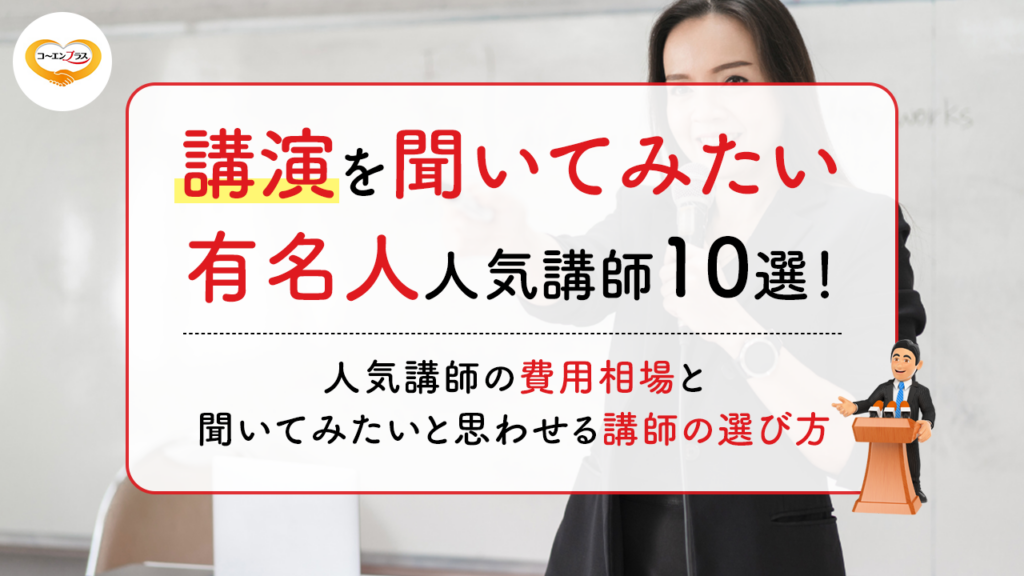AI研修とは?法人向けの内容や対象者、eラーニングやオンラインを用いた開催方法も解説
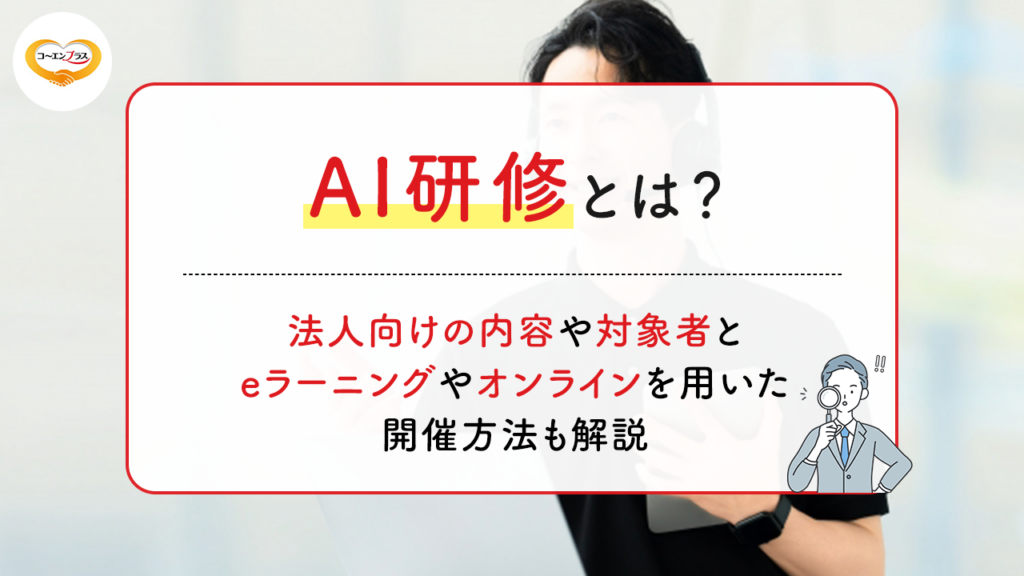
AI研修とは、企業や団体がAIに関する内容を学び、業務に活用することを目的とした教育プログラムです。そんな注目のAI研修ですが、「どんな内容を学ぶの?」「対象者は?」と思う方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、AI研修とはどのような内容か詳しく解説します。また、対象者とそれぞれの研修内容、開催方法も併せて紹介します。この記事を読めば、自社に適したAI研修を判断できるので、これからAIの活用を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
コンテンツ目次
講演会の講師依頼ならコーエンプラスにお任せください!

コーエンプラスでは、講演会を開きたい方に向けて、ビジネスに向けた社内研修の講演会から芸能・文化人、スポーツ選手まで幅広いジャンルの講師をご紹介可能です。
講演会、その日のためにベストマッチングの提供をお約束します。コーエンプラスには、下記の3つの強みがあり、お客様に満足いただけるサービスをご提供しています。
- 現場主義
- 豊富な経験と実績
- 親身な対応
来場者にご好評いただき、主催者にとって満足できる講演を目指すためには、まず主催者、講師、弊社の一体化が必要不可欠です。同じ目標に向かい、講演を成功させるための裏方作業を、私たちコーエンプラスがお引き受けいたします。主催者へのアドバイス、講師の移動やスケジュール調整など、細やかな所にまで気配りし、講演を成功へと導きます。
現場主義を徹底しているコーエンプラスでは、講師のベストマッチングに自信があります。
まずはお問い合わせください。
AI研修とは

AI研修とは、生成AIを含む人工知能技術の知識や実際の業務で使えるスキルを習得するための教育プログラムです。組織内のAIリテラシーの向上やDX推進を目的とし、プロンプト設計や業務適用、リスク管理など幅広いテーマで実施されます。
組織がAI研修を導入する背景には、急速に進展するAI技術に追随し、競争力の維持や向上といったニーズがあります。AIを活用した人材育成は、単なる技術理解を超えて業務変革や新たな価値創造を支える基盤として重要です。
法人向けのAI研修の主な内容(テーマ)
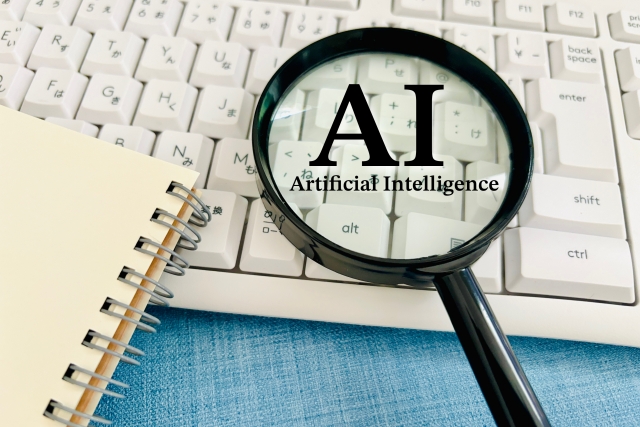
AI研修の主な内容は以下のとおりです。
- 生成AIの基礎と最新の動向
- 生成AIの活用法
- 生成AIを用いた経営戦略
- 中小企業向けの生成AI
- AI時代における働き方
1つずつ解説します。
生成AIの基礎と最新の動向
生成AIの基礎とは、AIの仕組みや進化してきた歴史、主要ツールの特徴や違いなどです。AIのアルゴリズムや原理、深層学習などを理解して身につけられます。
さらに、常に進化し続けるAIのアップデート情報の把握も必要です。今後の動向も学ぶことで、生成AIのトレンドを把握できます。
生成AIの活用法
業務現場での生成AI活用法では、文章生成や企画アイデアの立案、画像生成など幅広い内容で展開されます。さらに、特定の業務領域で応用する方法や知識を学ぶことも可能です。
生成AIの活用法がテーマの場合、デモンストレーションが実施されることが多く、実際にツールを操作して身につけられます。
生成AIを用いた経営戦略

生成AIを用いた経営戦略では、AIを使った経営観点からの活用法を学びます。AIの活用方法を理解した後は、ビジネスにどのように活かすかを考えることが重要です。
AIを用いて今までになかった新商品を開発したり、企業の改革案を提案したりなどビジネスに活かすと、市場で有利になる可能性があります。
中小企業向けの生成AI
中小企業向けのAI研修には、大企業とは異なる課題やリソース事情を踏まえた、実践的な内容が含まれます。具体的には、コストを抑えながらも高い生産性を実現するためのAI活用法や、少人数でも導入できるAI自動化の仕組みなどです。
この研修を通じて、中小企業でもAI導入による業務効率化や競争力向上が可能であることを理解できます。
AI時代における働き方
AI時代における働き方をテーマとした研修では、生成AIがもたらす業務の変化や人間が担うべき新たな役割を中心に学びます。
単なる業務の自動化だけでなく、共創型の働き方が重要視されています。AIと人間の協働における倫理的視点や情報リテラシーも取り上げられ、組織としての生産性と柔軟性を両立させることを目的としています。
AI研修のメリット

AI研修を実施する主なメリットは、以下のとおりです。
- AIを活用した業務効率化
- 従業員のスキルアップ
- 新しい価値の創造
1つずつ詳しく解説します。
AIを活用した業務効率化
AI研修で社員が生成AIを活用する技術を習得することで、日常の業務を効率化できるようになります。適切なAI研修を受けると、組織の効率化によってコスト削減も可能です。
具体的には、AIを補助ツールとして活用することで定型文書の生成や要約、翻訳や重複タスクの修正など業務負担を軽減できます。こうした効率化により、社員がより創造性の高い業務にリソースを割けるようになります。
従業員のスキルアップ
AI研修を実施すれば、従業員一人ひとりのAIリテラシーと技術理解が底上げされます。AI技術の活用方法を習得することで、プロンプト設計力やAI倫理観、ツールの選定なども可能です。
スキルアップした社員は自律的にAI活用を提案し、実行できるようになり、組織全体の底力を押し上げる人材育成にもつながります。
新しい価値の創造
AI研修を通じて技術的な理解と実践経験が積まれると、既存ビジネスの枠を超えた新たな価値やサービスが生まれる可能性が高くなります。具体的には、生成AIを用いた商品やサービスの企画、社内業務変革などです。
これにより、単なるコスト削減だけでなく、企業の競争力を高めるきっかけとなります。
AI研修の対象者と研修内容

AI研修の対象者は、以下のとおりです。
- 経営者
- 管理職
- DX推進担当者
- 全社員
それぞれの研修内容も併せて解説します。
経営者
経営者向けのAI研修では、AIを用いた経営戦略とDX推進に必要な考え方を学びます。経営者はツールの使い方よりも、ビジネスモデル変革や投資判断など、AIをどのように活用するか経営の観点から学ぶことが重要です。
管理職
管理職向け研修では、部門やチームを率いる視点から、AI活用とチームマネジメントの両立をテーマに学びます。AI時代のマネジメントを習得し、チーム力をアップさせることが主な目的です。
DX推進担当者
DX推進担当者向けには、より技術と実務に近い内容が求められます。テーマは生成AIを業務に落とし込む実践ノウハウやケーススタディ、導入手順や展開方法などが中心です。課題をAIでどのようにして解決するか、企画に活かすかなど、実践的な内容を学びます。
全社員
全社員向け研修では、AI・生成AIの基本的な内容やリスク、業務への適用例やプロンプト活用の初級演習などを中心に学びます。全社員研修ではAIに慣れ、組織内でAI活用を浸透させる土台づくりを図ることが目的です。
以下の記事では、組織の階層別に実施する研修を解説しているので、ぜひ併せてご覧ください。
AI研修の実施方法

AI研修の実施方法は以下のとおりです。
- 講師を招いた対面式
- オンライン研修
- ハイブリッド研修
- eラーニング
- パネルディスカッション
1つずつ解説します。
講師を招いた対面式
講師を招いた対面式では、ワークショップや質疑応答が可能なため、より深くAIを学べます。デモンストレーションが実施されることもあり、集中しやすい点がメリットです。
ただし、会場の手配やスケジュール管理、講師の手配などが負担になりすぎないように注意が必要です。 また、リハーサルの実施は成功につながりやすくなります。
以下の記事では、AIの講演会におすすめの講師を10名紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。
オンライン研修
オンライン形式のAI研修は、ウェブ会議ツールを活用するため、受講者が場所に縛られずに参加できる点が強みです。
ただし、受講者の通信環境の違いや、集中力の低下などにも配慮が必要です。これらのデメリットを補うために、小グループに分けたブレイクアウトルームでの演習が推奨されています。

ハイブリッド研修
ハイブリッド研修とは、対面とオンライン研修の双方を組み合わせて同時、または段階的に進める形式です。受講者は会場参加かオンライン視聴を選択できるため、距離やスケジュールの制約を受けにくいメリットがあります。
ハイブリッド研修には「ハイフレックス型」「ブレンド型」「分散型」があり、用途や対象者に応じて使い分けられます。
eラーニング
eラーニング形式のAI研修は、受講者が場所や時間を選ばず、自分のペースで学べる点が特徴です。さらに、eラーニングは反復視聴による復習のしやすさや学習進捗の可視化といったメリットがあります。
ただし、受講者のモチベーションや疑問への即時対応が難しい点、ネット環境に左右される点などを検討する必要があります。
パネルディスカッション
パネルディスカッションは、複数の専門家や実務者がテーマをもとに意見交換し、参加者と対話的に議論を深める形式です。AI研修やセミナーでは、講演内容を受けて補足的視点を提供したり、疑問点を掘り下げたりする場として活用されます。
パネルディスカッションは、多様な視点が一堂に会することで、議論の幅が広がるメリットがあります。ただし、テーマ設定の明確化やモデレーターの司会力、時間配分や参加者からの質問の機会設計など運営面の工夫が不可欠です。
AI研修を実施する流れ

AI研修を実施する際のおおまかな流れは、以下のとおりです。
- 目的を明確にする
- カリキュラムを作る
- 研修の実施
それぞれ順番に解説します。
1.目的を明確にする
AI研修を始める際は、実施する目的を明らかにすることが重要です。研修の方向性や内容がぶれないように、経営課題と照らし合わせる必要があります。具体的には業務効率化や新規事業創出、人材育成やAI文化の浸透など、どの成果を重視するかを定めることが大切です。目的を明確にすることで、対象者やテーマ、講師の選定などが進められます。
2.カリキュラムを作る
目的が定まったら、カリキュラムを作成します。カリキュラムの例としては、基礎を学ぶ研修なら「AIの歴史」や「生成AIとは何か」といった内容が一般的です。応用であれば、デモンストレーションやワークショップ形式を取り入れると、伝わりやすい傾向にあります。対象者や企業の課題に応じて、最適なカリキュラムを作成することが重要です。
3.研修の実施
カリキュラムが整ったら、研修の実施です。実施段階では、進行管理や、受講者の理解度の確認とフォロー体制などが必要です。生成AI研修プログラムでは、実務演習やプロンプト設計演習などのワークショップを織り交ぜている例が多い傾向にあります。また、実践してフィードバックを得ながら、本格展開につなげる設計も推奨されています。
以下の記事では、研修を開催する際の準備に関する内容を解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
まとめ

この記事では、AI研修とは何か、詳しく解説しました。
AI研修は、AIの基礎や活用方法を学び、業務に活かすことを目的に実施されます。研修のテーマは対象者によって異なり、基本的な内容の他にも経営戦略や中小企業向けの生成AI、AIと共にどう働くかなど多岐にわたります。
AIを業務に活かすには、最新の動向を把握しておくことも大切です。この記事を参考に、組織の課題や目的に応じたAI研修を実施し、業務効率化と競争力を身につけましょう。
講演会の講師依頼ならコーエンプラスにお任せください!

コーエンプラスでは、講演会を開きたい方に向けて、ビジネスに向けた社内研修の講演会から芸能・文化人、スポーツ選手まで幅広いジャンルの講師をご紹介可能です。
講演会、その日のためにベストマッチングの提供をお約束します。コーエンプラスには、下記の3つの強みがあり、お客様に満足いただけるサービスをご提供しています。
- 現場主義
- 豊富な経験と実績
- 親身な対応
来場者にご好評いただき、主催者にとって満足できる講演を目指すためには、まず主催者、講師、弊社の一体化が必要不可欠です。同じ目標に向かい、講演を成功させるための裏方作業を、私たちコーエンプラスがお引き受けいたします。主催者へのアドバイス、講師の移動やスケジュール調整など、細やかな所にまで気配りし、講演を成功へと導きます。
現場主義を徹底しているコーエンプラスでは、講師のベストマッチングに自信があります。
まずはお問い合わせください。