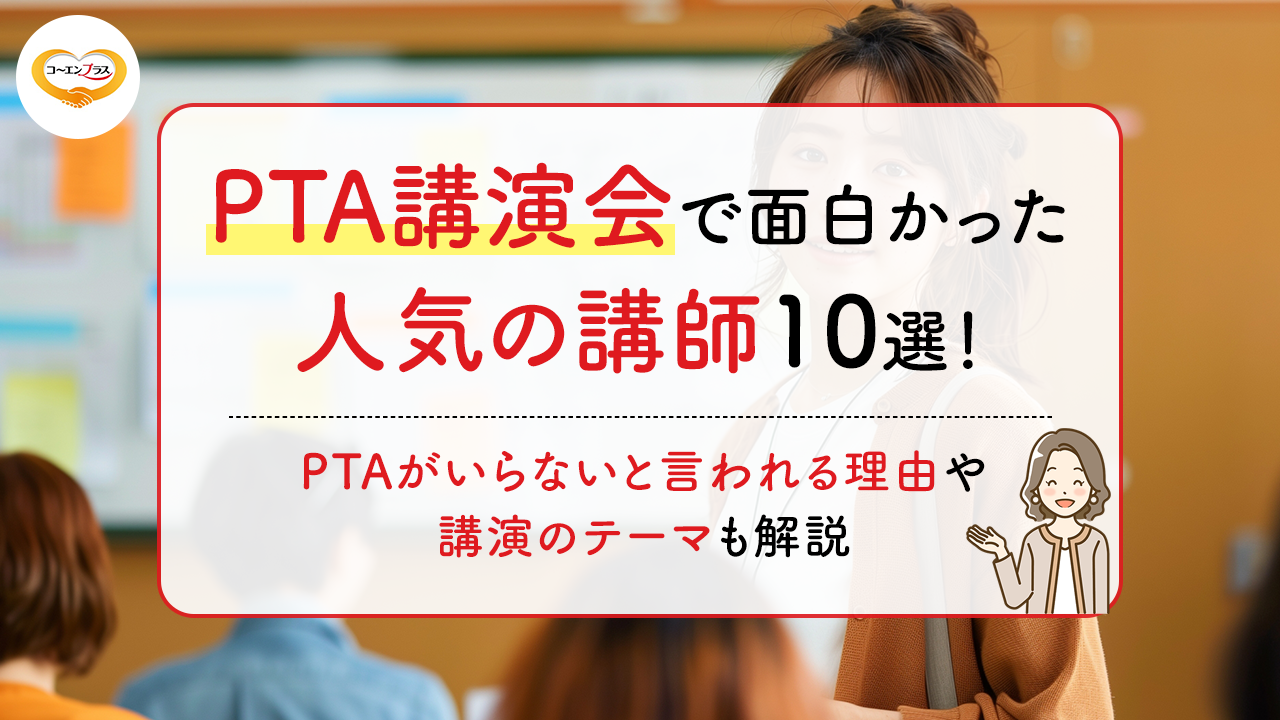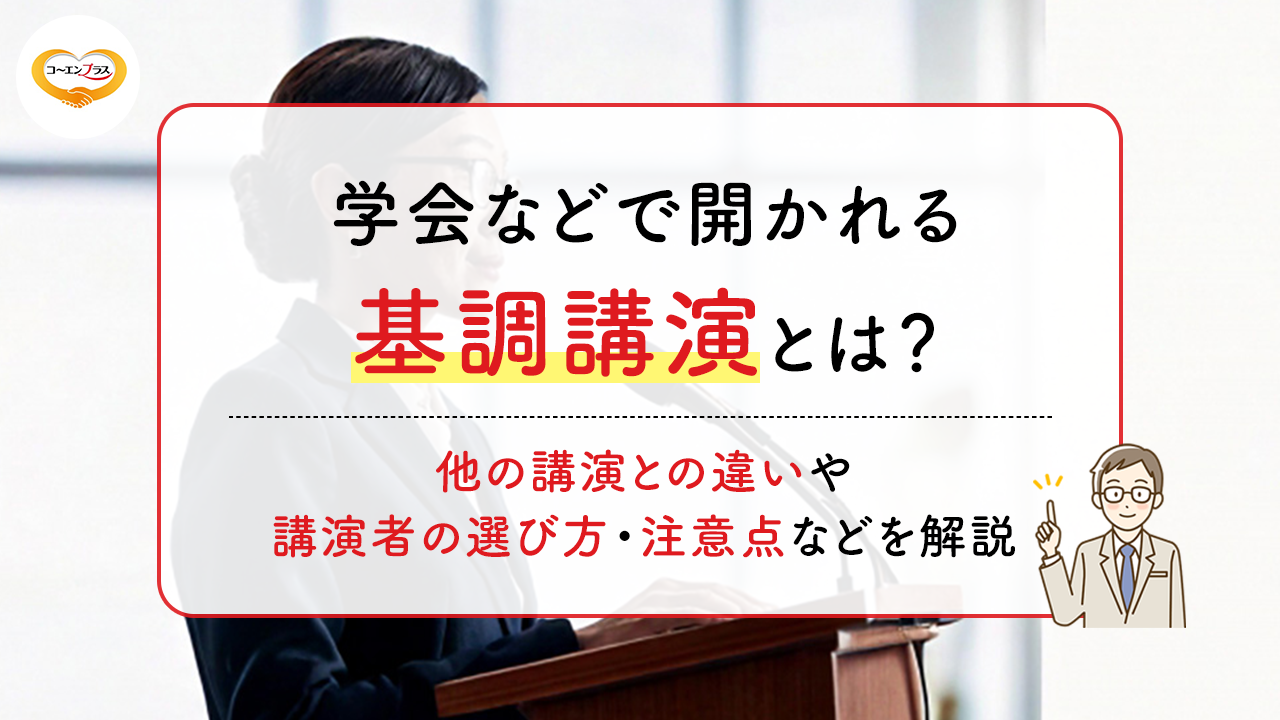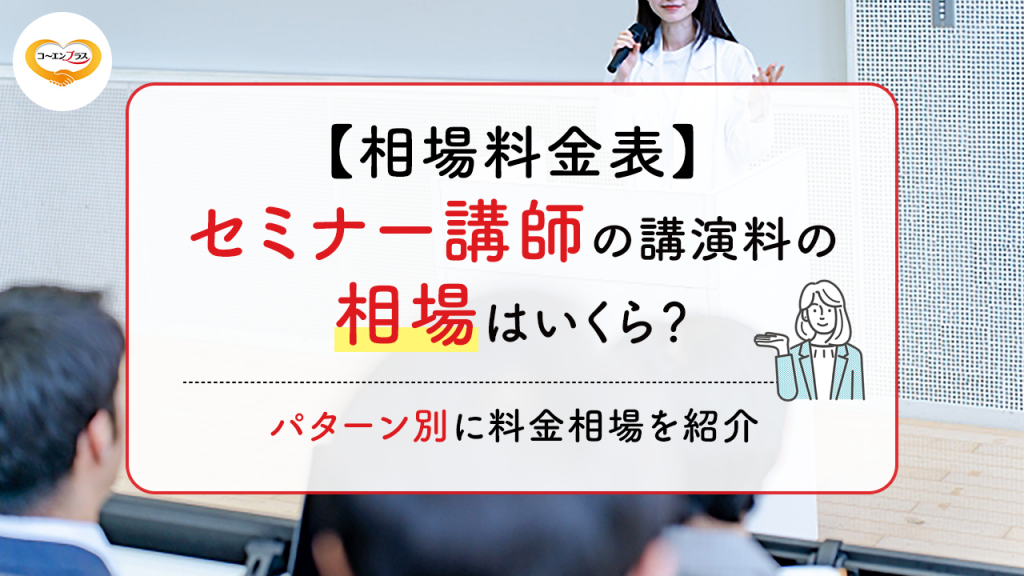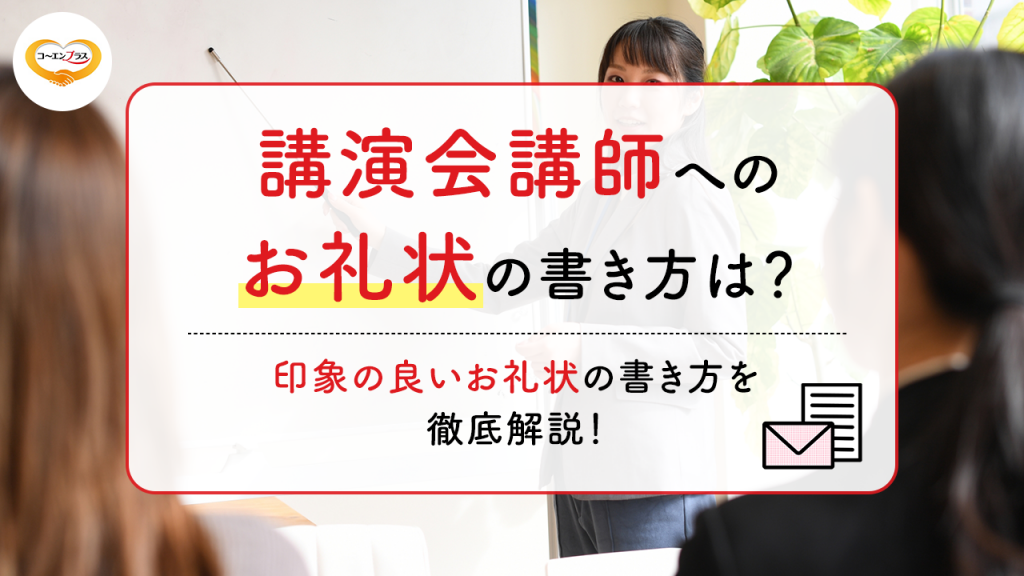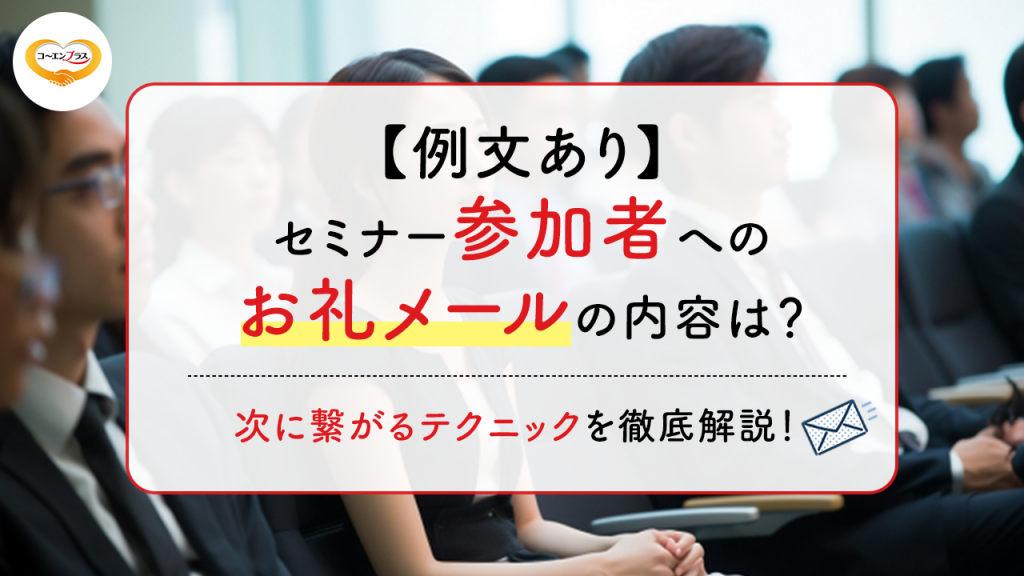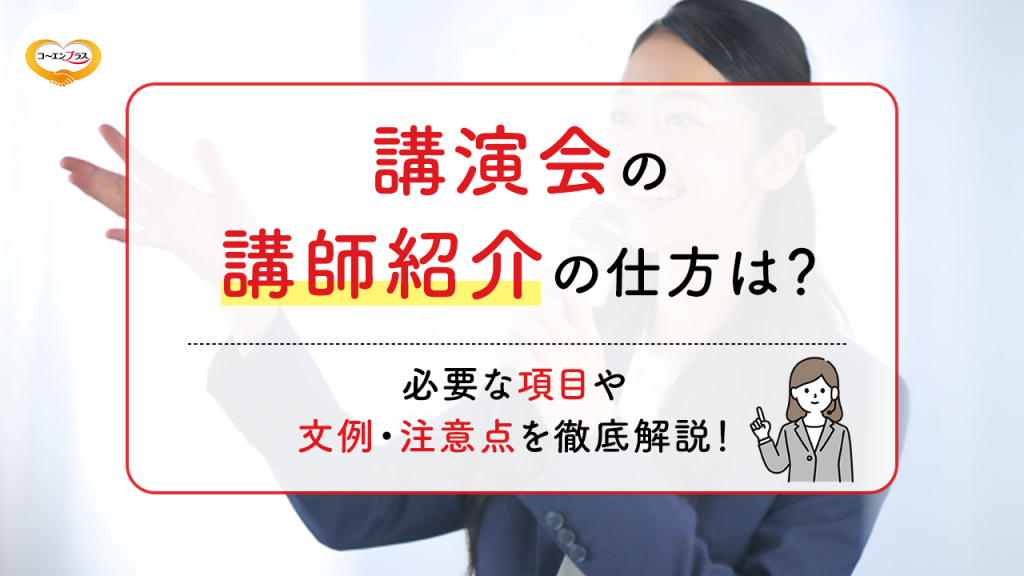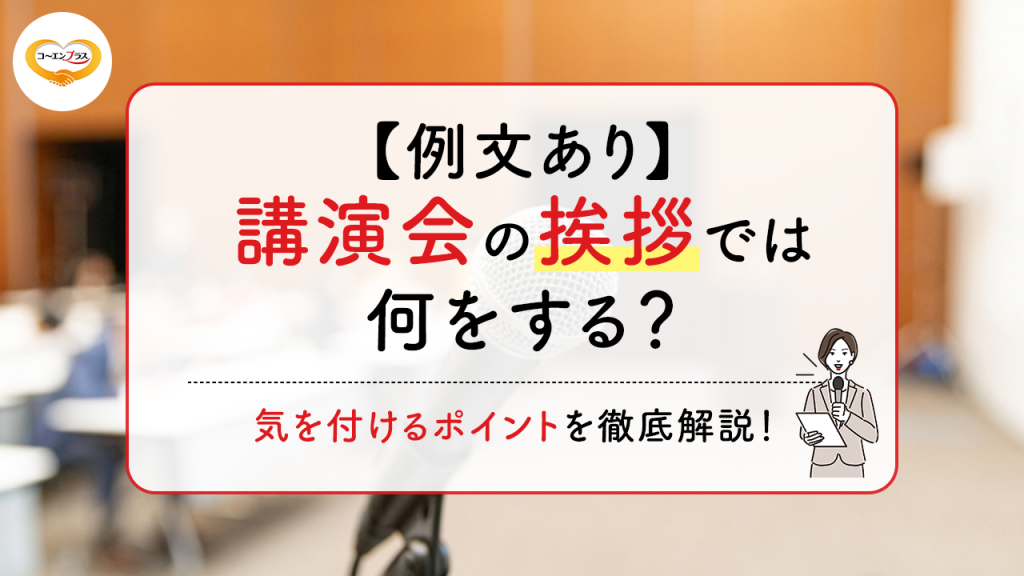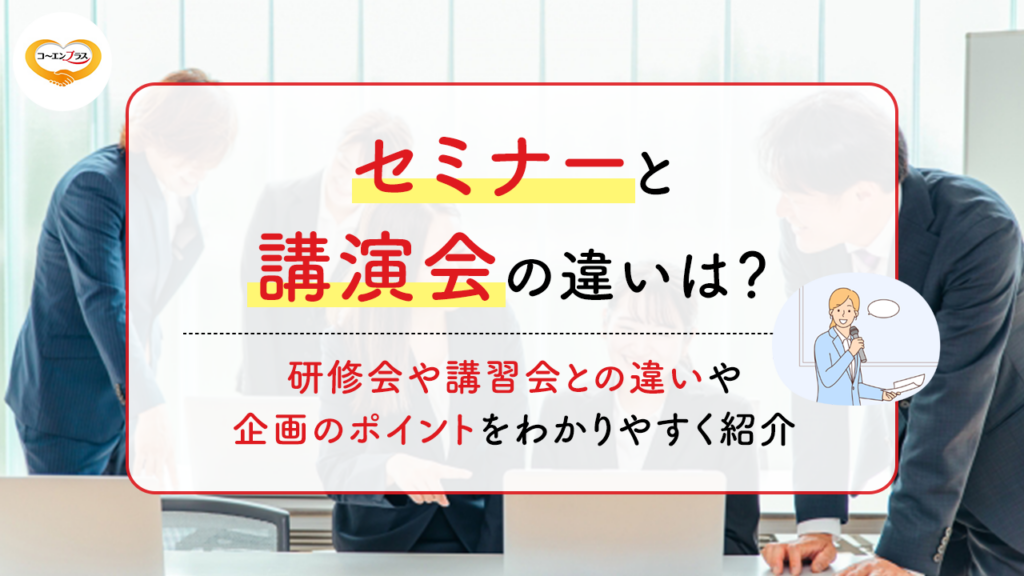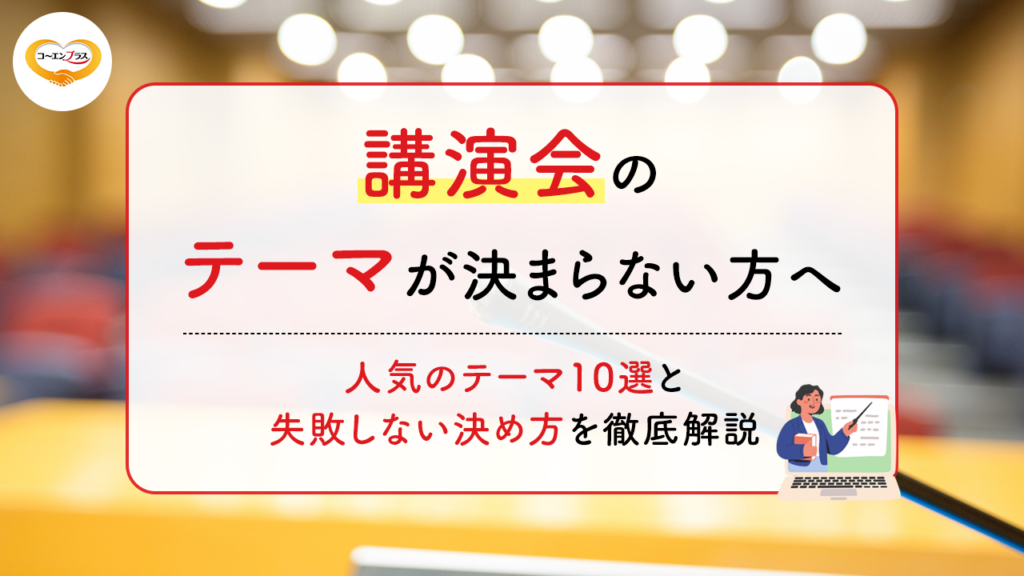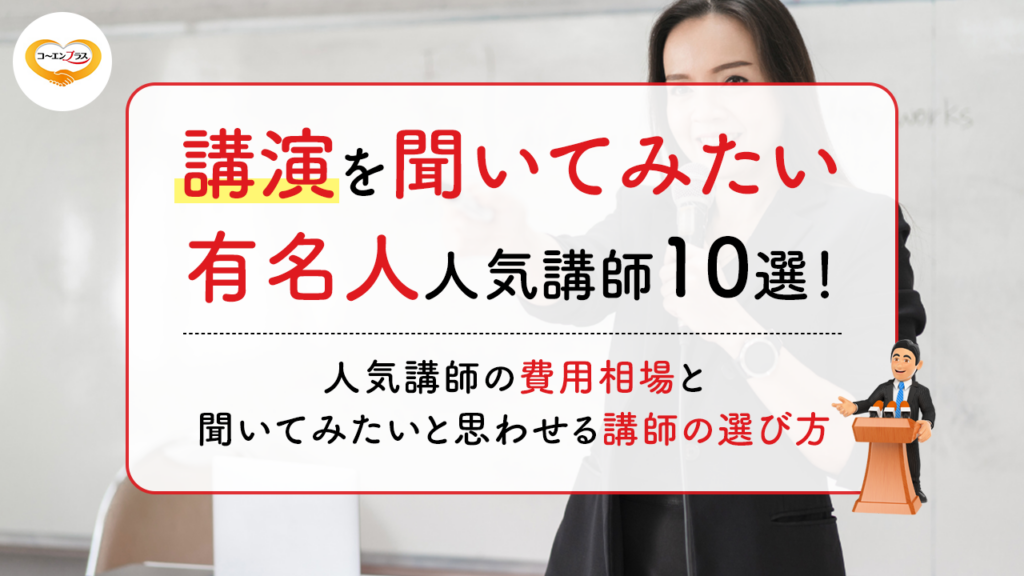シンポジウムと講演会の違いは?学会・パネルディスカッション・フォーラムとの違いとやり方も解説
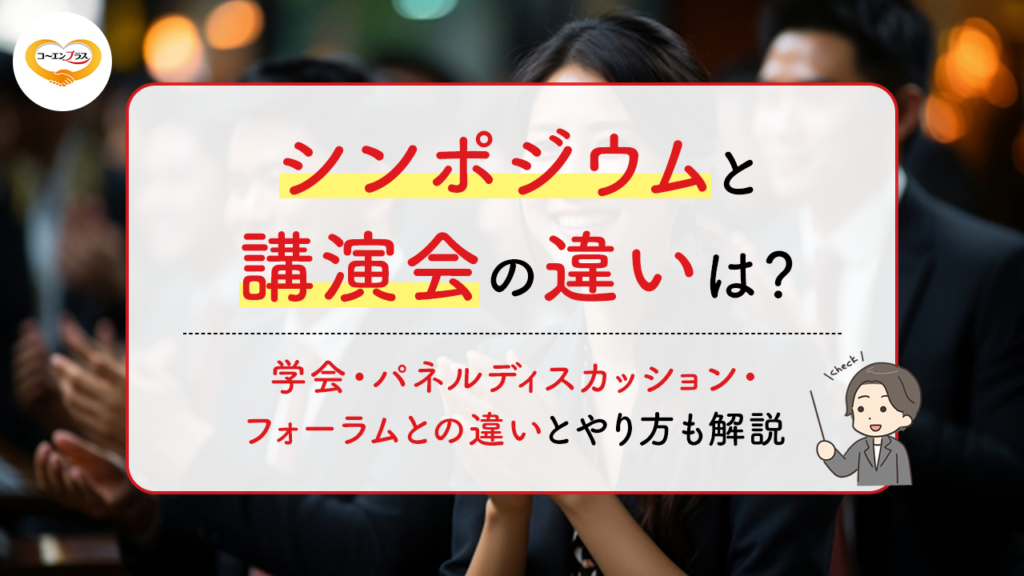
シンポジウムは、討論会や研究を発表する場で、意見交換の際に用いられます。そんなシンポジウムですが、「他の講演会との違いがわからない」と思う方も多いのではないでしょうか。
今回の記事では、シンポジウムと講演会の違いを解説します。また、他のイベントとの違いとシンポジウム開催のやり方も併せて紹介します。
この記事を読めば、シンポジウムとは何か理解できるため、参加予定の方や開催を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
コンテンツ目次
講演会の講師依頼ならコーエンプラスにお任せください!

コーエンプラスでは、講演会を開きたい方に向けて、ビジネスに向けた社内研修の講演会から芸能・文化人、スポーツ選手まで幅広いジャンルの講師をご紹介可能です。
講演会、その日のためにベストマッチングの提供をお約束します。コーエンプラスには、下記の3つの強みがあり、お客様に満足いただけるサービスをご提供しています。
- 現場主義
- 豊富な経験と実績
- 親身な対応
来場者にご好評いただき、主催者にとって満足できる講演を目指すためには、まず主催者、講師、弊社の一体化が必要不可欠です。同じ目標に向かい、講演を成功させるための裏方作業を、私たちコーエンプラスがお引き受けいたします。主催者へのアドバイス、講師の移動やスケジュール調整など、細やかな所にまで気配りし、講演を成功へと導きます。
現場主義を徹底しているコーエンプラスでは、講師のベストマッチングに自信があります。
まずはお問い合わせください。
シンポジウムとは

シンポジウムとは、特定のテーマに対して専門家や有識者が意見や研究成果を発表する場です。語源は古代ギリシャ語の「symposion」からきており、「ともに酒を飲み語る場」といった意味があります。
シンポジウムは、本来、自由で知的な対話の場とされていました。しかし、現代ではフォーマルな場とされる傾向にあります。形式は複数人の登壇者が発表した内容に、参加者が質問するスタイルが一般的です。
シンポジウムは学会・自治体主催のイベント・企業のブランディング施策など、多様な分野で活用されています。
講演会との違い

講演会とシンポジウムの違いは、意見交換や交流を目的としていない点です。講演会の最後に質疑応答の時間が設けられることもありますが、意見交換とは異なります。
シンポジウムが登壇者と参加者により作られる場なのに対し、講演会は1人の講師がテーマに沿って話すスタイルが一般的です。講演会は講師の知識や経験を聞いて学び、新しい知識や課題に対するヒントを得ることを目的としています。
講演会については、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ併せてご覧ください。
シンポジウムと他のイベントの違い

ここからは、シンポジウムと以下のイベントとの違いを解説します。
- 学会
- パネルディスカッション
- フォーラム
- カンファレンス
- 座談会
1つずつ詳しく解説します。
シンポジウムと学会の違い
シンポジウムは学会とは異なり、幅広い層の参加者が対象です。学会は専門家が研究の成果を発表して議論する場で、学術的な内容をテーマに展開されます。そのため、参加者は同じ分野の関係者に限られることがほとんどです。
シンポジウムは学術だけでなく、さまざまなテーマで開催されます。ビジネスや社会的な問題がテーマになることもあり、特定の分野に縛られていない点がシンポジウムの特徴です。
シンポジウムとパネルディスカッションの違い
シンポジウムは発表の後に参加者から意見や質問がありますが、パネルディスカッションは参加者も含めて議論を展開します。
パネルディスカッションでは参加者をパネラーまたはパネリスト、司会役をコーディネーターまたはファシリテーターと呼びます。パネラーが意見を述べた後に、コーディネーターを通して議論するスタイルが一般的です。
シンポジウムの参加者は聞くだけでも良いですが、パネルディスカッションは集団で意見交換が繰り広げられます。
シンポジウムとフォーラムの違い

シンポジウムがさまざまな意見を出して知識を深めるのに対し、フォーラムは結論を明らかにする目的で開催されます。フォーラム(forum)を日本語に訳すと、「集会所」といった意味をもつため、場所を示す際に使用されることもあるようです。
シンポジウムとフォーラムは、意見交換をする点では同じですが、厳密にいうと最終目的が異なります。
シンポジウムとカンファレンスの違い
シンポジウムとカンファレンスは、参加者との関係性が異なります。シンポジウムでは発表されたことに対して第三者が意見や質問しますが、カンファレンスでは組織内で意見交換や報告がなされます。
同じ組織内で会議をする際に、「〇〇カンファレンス」と題して開かれるのが一般的です。
シンポジウムと座談会の違い
シンポジウムが大規模で開催されるのに対し、座談会は少人数で開かれる非公開、または半公開の自由討論の場です。座談会にもテーマはありますが、会話形式で進行し、議論より話し合いのイメージが強い傾向にあります。
シンポジウムは多くの聴衆を前にした知的な場、座談会は少人数での気軽な対話の場といった違いがあります。
シンポジウムのパネリストとは

シンポジウムにおけるパネリストとは、専門的知見や実務経験をもとに意見を述べる登壇者を指します。シンポジウムで発表した後に、パネルディスカッション形式で開かれるイベントもみられます。
パネリストは、特定の分野に高度な知識を持つ人物や、行政関係者などで構成されるのが一般的です。ただし、専門性だけでなく、対話力も重視されます。
パネリストが異なる背景や立場から意見を交わすことで、参加者に新たな視点を与え、テーマに対する理解を促します。
シンポジウム開催のやり方

シンポジウムを開催する際は、以下の内容で進めます。
- 概要を決める
- 場所の選定
- 登壇者の選定
- プログラムの構成を作成
- 告知
- 備品の準備
1つずつ解説します。
概要を決める
シンポジウムの準備は、企画の土台となる概要の決定から始まります。決める内容は、主に以下のとおりです。
- テーマ
- 目的
- 規模
- 予算
- 日時
これらの内容を先に決めることで、会場選びや登壇者の選定、広報戦略などがスムーズに進みます。テーマの選定は参加者の興味を引く内容にすることで、顧客の獲得やブランディング効果の向上にも期待できるため重要です。
場所の選定
概要が固まったら、予算に見合った会場選びに移ります。シンポジウムに適した会場は、アクセスの良さや充実した設備、参加人数に応じた適切な広さがある施設です。
控え室や受付スペース、同時通訳ブースなど、イベントの規模や登壇者の要件に応じた施設条件もチェックが必要です。宿泊施設が近くにあると、遠方からの参加者も獲得できる可能性があります。
以下の記事では、会場のレイアウトについて解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
登壇者の選定

シンポジウムにおける登壇者は、イベントの内容と質を左右する非常に重要な存在です。主催者が設定したテーマと合致し、参加者にとって有益な知見や視点を提供できる人物を選ぶ必要があります。
多様な意見が交わされるシンポジウムでは、立場や背景が異なる登壇者をバランスよく配置するのが理想的です。研究者と実務者、行政と民間など幅広い視点を交えることで、内容の深みと多角性が生まれます。
人気がある登壇者ほどスケジュールの調整が難しいため、早めに依頼することが大切です。
プログラムの構成を作成
登壇者や会場が決まったら、全体のタイムスケジュールを含めたプログラムの構成を作成します。プログラムの流れは「基調講演→報告・発表→パネルディスカッション→功績者報告→閉会のあいさつ」が一般的です。流れや構成は、主催者の目的に応じて柔軟に設計します。
注意したいのは、各セッションの時間配分です。さらに、ディスカッションが一方的にならないように、パネラーが介入するタイミングを登壇者にも共有しておく必要があります。
プログラムは運営用・登壇者用・配布用を用意し、当日の運営がスムーズに進むように整えておくと安心です。
告知
シンポジウムを成功させるには、告知も重要です。公式サイトやイベント専用ページで、開催日時・場所・テーマ・登壇者のプロフィール・申込方法などの基本情報を分かりやすく掲載する必要があります。
ターゲット層に応じて、告知方法を併用するのも効果的です。通常の告知と併せて、メール配信やニュースレター、SNSなども利用すると集客に期待できます。
備品の準備
備品を準備する際は、備品リストを作成し、必要なアイテムを明文化することがポイントです。マイクやスクリーン、プロジェクターなどの備品をリストアップして、当日使用できるか事前にチェックすることをおすすめします。
会場の通信環境や設備、レンタルの有無も確認しておくことも重要です。
以下の記事では、講演会の準備について企画のポイントやチェックリストの作成方法などを解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
シンポジウムをスムーズに開催するコツ

シンポジウムは、以下の点に気をつけるとスムーズに開催できます。
- 早めに準備する
- 業者に依頼する
- 運営用のマニュアルを用意する
それぞれ詳しく解説します。
早めに準備する
シンポジウムの準備にあたって、会場の手配や登壇者への依頼は早めにすることが重要です。特に、新年度に開催する際は、混雑する傾向にあります。日程・テーマ・開催形式などを決めたら、登壇者に仮打診をしておくことも大切です。
早めに準備することで、想定外のトラブルにも柔軟に対応できます。
業者に依頼する
自社でリソースが不足している場合は、専門のイベント業者に委託するのも効果的です。シンポジウムに特化した業者は、会場設営から受付対応、登壇者の選定までトータルでサポートしてくれます。
コストは発生しますが、リスクの軽減と品質の確保、業務削減に期待できるためスムーズに進められます。
運営用のマニュアルを用意する
当日の混乱を防ぐために、運営マニュアルの作成は欠かせません。マニュアルには受付や誘導方法、トラブル時の対応手順などを具体的に記載しておくことが大切です。
想定外の事態にも備え、緊急連絡先や控え室の案内、登壇者の到着時間なども盛り込んでおくと安心できます。マニュアルを用意しておくことで、当日の連携がスムーズになります。
まとめ

今回の記事では、シンポジウムと講演会の違いを詳しく解説しました。
シンポジウムは、複数の専門家が1つのテーマに多角的な視点で意見を交わす、公開討論の場です。講演会は、1人の講師が参加者に知識や経験を共有し、気付きやヒントを与えるイベントを指します。
学会やパネルディスカッションなどとの違いも明確にすることで、企画の方向性をたてやすくなります。この記事を参考に、シンポジウムを開催する意義を理解して、参加者に実りある場を提供してみてください。
講演会の講師依頼ならコーエンプラスにお任せください!

コーエンプラスでは、講演会を開きたい方に向けて、ビジネスに向けた社内研修の講演会から芸能・文化人、スポーツ選手まで幅広いジャンルの講師をご紹介可能です。
講演会、その日のためにベストマッチングの提供をお約束します。コーエンプラスには、下記の3つの強みがあり、お客様に満足いただけるサービスをご提供しています。
- 現場主義
- 豊富な経験と実績
- 親身な対応
来場者にご好評いただき、主催者にとって満足できる講演を目指すためには、まず主催者、講師、弊社の一体化が必要不可欠です。同じ目標に向かい、講演を成功させるための裏方作業を、私たちコーエンプラスがお引き受けいたします。主催者へのアドバイス、講師の移動やスケジュール調整など、細やかな所にまで気配りし、講演を成功へと導きます。
現場主義を徹底しているコーエンプラスでは、講師のベストマッチングに自信があります。
まずはお問い合わせください。