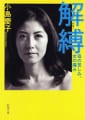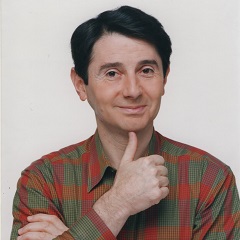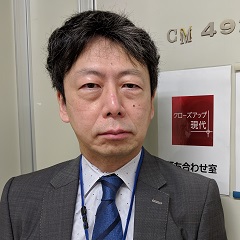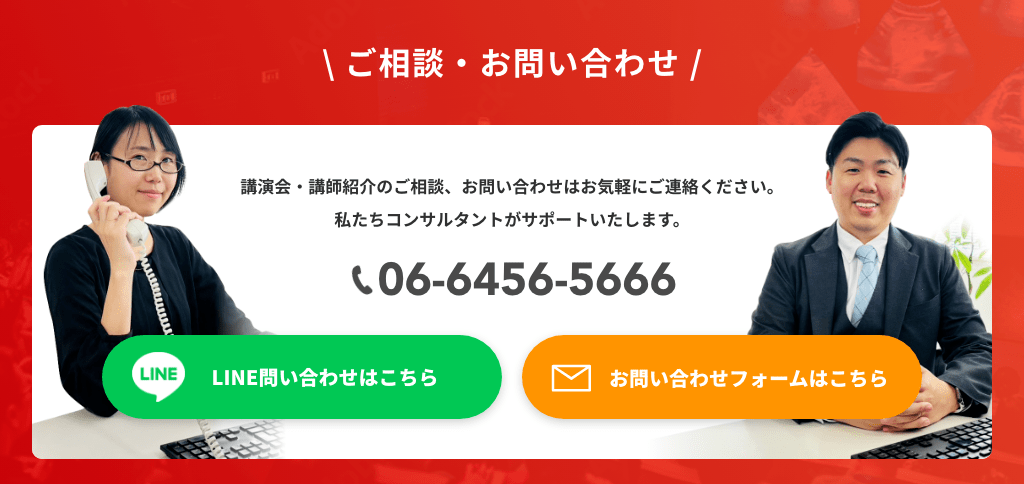こじま けいこ小島 慶子
- 肩書き
- エッセイスト
メディアパーソナリティ
昭和⼥⼦⼤学現代ビジネス研究所特別研究員 - 出身・ゆかりの地
- 海外
この講師のここがおすすめ
プロフィール
1995年学習院大学法学部政治学科卒業
TBS入社 アナウンサーとしてテレビ・ラジオに出演
1999年第36回ギャラクシー賞 ラジオ部門DJパーソナリティー賞受賞
2010年独立 各種メディア出演のほか、執筆・講演活動を精力的に行っている
2014~2023年オーストラリア・パースに教育移住自身は日本で働き、夫と二人の息子が暮らすパースと往復する生活を送った
2015年~2020年朝日新聞パブリックエディター
2017年~2025年東京大学大学院情報学環客員研究員(メディア表現とダイバーシティ:MeDi)
2019年~昭和女子大学現代ビジネス研究所特別研究員
2024年~息子たちが海外の大学に進学
自身は10年間の⼆拠点生活を終えて、日本に定住 新たに仕事の幅を広げている
現在、文化放送「大竹まことのゴールデンラジオ」の火曜レギュラーを務める
主な講演のテーマ
- 仕事と人権〜ジェンダー平等からはじまる、これからの生き方、働き方
SDGs(持続可能な開発目標)の17の目標のうち、5番目に謳われているジェンダー平等。
残念ながら、日本は世界の中でも際立ってジェンダー格差の大きな社会です。
育児と仕事の両立、キャリア形成など、女性の悩みは尽きません。男性も、今は家事や育児、介護をしないと暮らしが成り立たない時代。
「男は仕事、女は家事育児」ではなく「男性も女性も、働きながら幸せになれる」社会が、日本を豊かにします。
アナウンサーとして放送局に勤めていた時、私もジェンダーの壁に悩みました。
共働きで子育てをしながら、労組の副委員長として働きやすい制度づくりにも携わりました。
独立後は、一家を支える片働きに。家族と生きることと働くことを真剣に考え、数多くのエッセイや本を執筆しています。
自身の体験をお話ししながら、これからの生き方・働き方について、前向きな提言をします。 - 絶体絶命は打ち出の小槌〜ピンチをチャンスにする発想法
人生には、予想もしないことが起きるもの。私にも、何度もそんなことがありました。
アナウンサーという憧れの仕事についたら、いきなり壁にぶつかって大迷走。出産後、仕事復帰を目前にして不安障害という病気に。育休から復帰したら、番組出演の仕事が激減。独立後には、夫が主夫になり片働きに。にもかかわらず教育移住を決断、夫と息子たちはオーストラリアに移住し、私は日本でひとり働き日豪を往復。その間には、コロナ禍で2年2ヶ月も家族と会えず、メンタルが限界に……。20代から現在まで、こんなはずではなかった!という予想外の出来事が何度もありました。変化の時には、誰でも不安になるけれど、失うものばかりではありません。悩みながら発想を切り替えて、ピンチをチャンスにしてきた経験をお話しします。 - 違いを尊ぶって、どういうこと?〜多様性は半径2メートルから
多様性、ダイバーシティと聞くと、慣れ親しんだ暮らしが変えられてしまうのではと不安に思う人もいるかもしれません。でも、多様性はずっと前から、ごく身近にあるものです。人種、ジェンダー、性的指向、身体、年齢などなど、誰でも「他の人との違い」がありますよね。何を幸せと感じるかも人それぞれです。違いを尊ぶ社会づくりは、身近な半径2メートルの世界にある違いに気づき、知ろうとすることから始まります。
私は、男性が圧倒的に多いテレビ業界で働いた経験があり、不安障害という病気を経験し、発達障害(ADHD)の当事者で、子育てをしたオーストラリアでは、少数派のアジア系移民という立場でした。「周りの人と違う」立場になって、それまでとは世界の見え方が変わりました。
違いのある人たちが一緒に暮らすには、知恵と想像力が必要です。私の体験をお話しすることで、みなさんの小さな気づきにつながれば嬉しいです。 - 「ふつう」ってなんだろう?〜発達障害と生きる
子どもの時から、大人たちに「どうしてふつうにできないの?」と言われることが多かった私。叱られることが多くて、困っていました。40歳を過ぎてから、発達障害の一つであるADHD(注意欠如多動症)であると診断され、自身の特性について理解が深まりました。発達障害に対する偏見をなくし、違いを尊ぶ世の中にしようと、エッセイやテレビなどで発信しています。
今は、ニューロダイバーシティ(脳・神経の多様性)という考え方も広まっています。障害について正しく知ること、今までの「ふつう」を捉え直すことで、新しい視点で人間を見ることができます。この世に同じ脳みそは一つもないのだから、違っていて当たり前だというとてもシンプルな答えに行き着くのです。自身の体験を、発達障害に詳しくない人にもわかりやすくお話ししています。講演を聴いた発達障害の当事者、支援者の皆様からも多くの共感の声を頂いています。 - 失敗しないグローバル教育〜子どもに必要な“生きる力”とは
留学や移住への関心が高まるにつれ、日本の学校でもIBコースなど、グローバル教育への取り組みが増えています。私は2014年、オーストラリアに教育移住しました。家族の拠点を西オーストラリア州・パースに移し、夫と息子たちはパース、私は東京で生活する二拠点家族に。息子たちは現地の公立小学校からハイスクール、大学へと進学しました。当時はまだ珍しかった教育移住や海外大学進学ですが、今では多くの方から相談を受けます。今なぜ、グローバル教育が注目されているのでしょうか。英語を身につけるだけでなく、広い視野で物事を捉え、変化に富んだ環境に柔軟に対応するには、自ら考え表現する力が必要です。私が教育移住を決断した理由と、海外での教育を通じて気づいた普遍的な学びの意義、そして日本で生活していても身につけられるこれからの時代に必要な“生きる力”について、具体的なエピソードを交えてお話しします。 - 更年期について話そう〜ついにその日がやってきた!
更年期は今や、大きな社会課題。女性も男性も、仕事や子育ての責任が重くなる時期に、体の大きな変化を迎えます。中には仕事を休む人や、辞めざるを得なくなる人も。
ホルモンに関する話だから、老化の話だから、人に言うのが恥ずかしい……と一人で抱え込むと、不調を悪化させてしまいかねません。早めに医師に相談して、同じ悩みを持つ仲間と繋がることが大切です。私も47歳の時に、それまで経験したことのない色々な不調に見舞われました。しばらく一人で悩んだ末にかかりつけの婦人科医に相談すると、女性ホルモンが減り始めていることが判明。「おお、これが噂の更年期!ついにその日がやってきたか」と思いました。今は、先生に相談しながら更年期症状を和らげる治療を受け、変化する体とうまく付き合いながら生活しています。
実は30代の頃に、ある決意をしました。当時は、テレビで女性の更年期が笑いのネタにされていました。女性出演者を揶揄ったり、中年女性が自虐で笑いをとったり。でも私は、大事な大事な体の話をそんなふうにバカにする風潮を変えたいと思いました。だから自分がその時を迎えたら、ちゃんと真面目に話そう!と思っていたのです。
それから15年ほど経って私が更年期を迎えた今では、真面目にオープンに語る場が増えてきました。職場での対応も始まっています。女性も男性も、年齢とともに体が変化します。
変化に気づき、医師とつながり、更年期を生きる自分を受け入れる。更年期を自然なこととして安心して語り合えるようにしたいですね。
私の体験をお話しし、悩んでいる人には決して一人ではないと知って欲しいです。 - 子育てはインタビュー〜あなたはだあれ?が子どもを伸ばす
人気女性誌『VERY』(光文社)で約10年間連載した子育てエッセイ『もしかしてVERY失格?!』ほか、多くの育児エッセイで読者の皆様から温かい共感のお声を頂いています。
子どもは思い通りにならない小さな「他者」。
私もたくさん悩みながら、息子たちから多くのことを学びました。親は良かれと思って、我が子を理想通りに育てたいと思ってしまいますが、まずは子どもに「あなたはだあれ?」と素直に向き合い、耳を傾けることが大切です。
仕事に追われて子供との時間がとれない、周囲と比べて焦ってしまう……そんな育児に悩む親たちに寄り添いながら、子どもの伸びる力を引き出すためにできることを、オーストラリアでの子育て経験も交えて語ります。 - 家族がつらいと言っていい〜あなたが幸せになるために
家族のことで悩んでいる人が、たくさんいます。親と会うのがつらい、家族といると苦しい。そんなこと言うと甘えているとか親不孝と言われてしまうのではないかと後ろめたく思ってしまう。つらいのに、期待してしまう。幸せになりたいだけなのに、どうして家族ってこんなにややこしいのでしょう。
私にも、そういうことがありました。生まれ育った家族との関係に悩み、摂食障害に。カウンセリング、不安障害の治療と、20年以上かけて家族との関係を捉え直しました。今もその途上です。
家族の問題は、社会の問題とも繋がっています。答えは一つではありません。私の場合はどうであったかをお話しすることで、同じ悩みをお持ちの方に何かのヒントになればと思います。