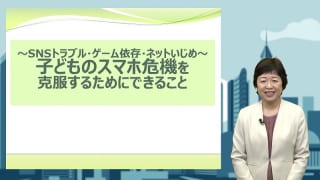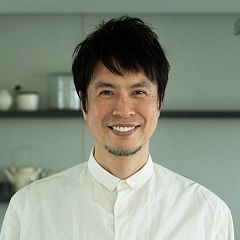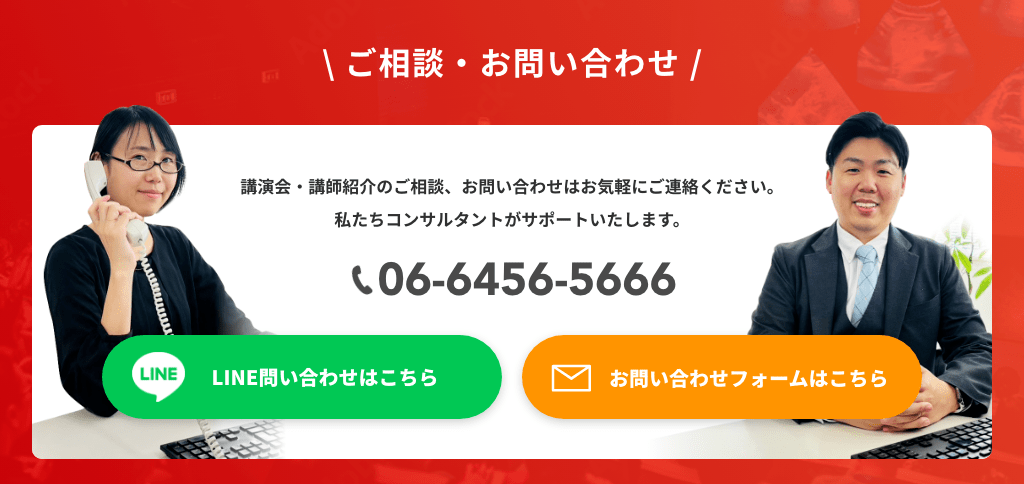いしかわ ゆうき石川 結貴
- 肩書き
- 作家/ジャーナリスト
- 出身・ゆかりの地
- 静岡県
この講師のここがおすすめ
作家・ジャーナリストの石川結貴さんは、子どもと子どもを取り巻く社会に常に焦点をあて問題を提起しつづけています。講演は、子どもとの繋がりを深めるためのルール作りなど、具体的な提言が満載!
「わかりやすく」現状を報告、「今できること」を提案、「少しの勇気と小さな行動力で変えられる」をモットーにSNS・ネット用語等に詳しくない方にも、言葉の意味を具体的に示して解説。丁寧でとても分かりやすいと好評です。
プロフィール
家族・教育問題、青少年のインターネット利用、児童虐待などをテーマに取材。
豊富な取材実績と現場感覚をもとに多数の話題作を発表している。
『スマホ危機 親子の克服術』(文春新書)では、子どものスマホ利用の実態報告とともに、具体的かつ実践的な対応方法を紹介。スマホやネットがもたらす数々の社会現象を追い、利便性の背後にある新たな問題を提起した『スマホ廃人』(同)は国公立大学入試問題に採用、中国でも翻訳出版されている。
親との関係性に苦しみながらも介護を担う子世代の実態を追った『毒親介護』(文藝春秋)、ビジネスケアラーとしての自身の在宅看取り経験を綴った『家で死ぬということ~ひとり暮らしの親を看取るまで』(同/第55回大宅壮一ノンフィクション賞候補作)などの著作では、現行の医療や介護、社会保障制度の問題も追及している。
貧困や虐待環境に置かれながら社会的に見棄てられる子どもの実態を描いた『ルポ 居所不明児童~消えた子どもたち』、『ルポ 子どもの無縁社会』などの著作は大きな反響を呼んだ。2015 年「日本子ども虐待防止学会新潟大会」(JaSPCAN)、「子ども虐待防止フォーラム」(厚生労働省)、2023 年「日本 PTA 連盟全国協議会広島大会」(日本 PTA 連絡協議会)など、大規模集会での講演者に選出されている。
出版のみならず、専門家コメンテーターとしてのテレビ出演、全国各地での講演会など幅広く活動する。日本文藝家協会会員
代表的な講演実績
2024年 京葉5市市議会議員合同研修会(千葉県内5市の市議会議長、市議会議員が一堂に会する研修会)
講演テーマ『孤立と虐待のない街づくり~傷つく子どもを支えるためにできること」
2024年 医療介護福祉政策研究フォーラム・第99回医療研究会(医療や介護政策に関わる専門家、研究者などを対象にしたオンライン研修会)
講演テーマ『家で死ぬということ~在宅死のリアルについて考える』
2023年 第71回日本PTA全国研究大会・広島大会(全国のPTA連絡協議会が合同で開催する研究大会)
講演テーマ『孤立と虐待のない街づくり~傷つく子どもを支えるためにできること』
2023年 第5回少年健全育成ボランティア大会(福岡県内の少年警察ボランティア等が一堂に会する研修会)
講演テーマ『スマホ世代の子どもとどう向き合うか』
2022年 埼玉県私立小中学校保護者会(埼玉県内の私立小中学校の保護者を対象にした研修会)
講演テーマ『子どものスマホ危機~SNS、ゲーム、動画、デジタル世代の子どもにどう向き合うか』
2022年 第5回日本小児科医会全国講演会(全国の小児科医を対象にしたオンライン講演会)
講演テーマ『子どもを取り巻く環境変化~デジタル化が及ぼす影響』
主なメディア出演
NHK 「あさイチ」「ニュースウッオッチ9」
日本テレビ 「バンキシャ!」
TBSテレビ 「ひるおび」「報道特集」
フジテレビ 「バイキングmore」
テレビ朝日 「ワイド! スクランブル」「報道ステーション」
主な著書
『スマホ危機 親子の克服術』(文藝春秋)
『スマホ廃人』(文藝春秋 国公立大学入試採用作品/中国翻訳出版)
『子どもとスマホ~おとなの知らない子どもの現実』(花伝社)
『家で死ぬということ~ひとり暮らしの親を看取るまで』(文藝春秋 第 55 回大宅壮一ノンフィクション賞候補作)
『毒親介護』(文藝春秋)
『ルポ 居所不明児童~消えた子どもたち』(筑摩書房)
『ルポ 子どもの無縁社会』(中央公論新社)
『誰か助けて~止まらない児童虐待』(リーダーズノート)
『愛されなかった私たちが愛を知るまで』(かもがわ出版)他多数
雑誌・新聞連載
毎日新聞社・サンデー毎日「孤家族のゆくえ」
共同通信「スマホ世代の子どもたち」
時事通信「つながりたい~子どもとスマホ」
主な講演のテーマ
【ネット・スマホ関連】
1. スマホ世代の子どもとどう向き合うか~SNS、ゲーム、ネットいじめの問題を考える
一般市民向け、人権擁護、PTA や教育関係者研修、青少年健全育成、民生児童委員研修向け
令和 4 年度「未成年者のインターネット利用環境実態調査」(総務省)によると、インターネットの平均利用時間(平日)は小学生(10 歳以上)3 時間 34 分、中学生 4 時間 37 分、高校生約 5 時間 45 小と長時間化、過去最多を記録しています。
低年齢のうちから YouTube などの動画視聴が習慣化し、オンラインゲーム(スマホゲーム)に没頭するあまり学業や健康に影響が生じるケースも少なくありません。
友達との交流は LINE や X(旧ツイッター)、Instagram などの SNS が主流となり、見知らぬ人を「友達承認」する子どもも増えています。
テキストメッセージ(文字のやりとり)だけでなく声で会話するボイス SNS、動画配信を通じて視聴者と交流するなど、子どもを取り巻く SNS 環境は大きく変化しています。
ネット上のいじめや誹謗中傷の被害も見過ごせません。「死ね」、「キショ(気持ち悪い)」などの暴言、噂話や個人の画像を拡散して嘲笑するような集団いじめも起きています。
子どもたちの状況が深刻化する一方で、家庭や学校、地域などは具体的な対応策を見出せていません。「ネットは危険」、「スマホを使いすぎるな」と言ったところで、何が危ないのか、どう改善すればいいのか、きちんと子どもに伝えられていないのです。
子どものスマホ利用に不安はあるが詳しい内容はわからない、自分はスマホに不慣れで子どもの状況が理解できない、そういう「スマホ弱者」のおとなでも、実のところできることはたくさんあります。
子どもたちはなぜゲームや動画視聴をやめられないのか、SNS でどんなトラブルが起きやすいのか、さまざまな問題の背景を解説し、具体的な対応策を提案します。
本講演を通じ、最新の状況を把握するとともに、家庭や地域でできる教育、子どもとの向き合い方について考えてみましょう。
2. 子どもが変わる実践的スマホ教育~デジタル・AI 社会を生きる子どもとどう向き合うか
小中高校PTA主催講演会向け
文部科学省が実施するGIGAスクール構想により、全国の小中学生に1人1台のデジタル端末(タブレット・ノートPC)が配布されています。さらに2020年からは、全国の公立中学校への「スマホ持ち込み」が条件付きで容認されました。
小学生が自由にタブレットを使える、中学生がスマホを学校に持ち込める、こうした時代において、あらたなネットリスク、スマホトラブルの増加も懸念されます。
友達を求めて利用したSNSでトラブルに巻き込まれる。過度なゲーム課金で大金を使ってしまう。チームを組んで闘うゲームで友達から仲間はずれにされる。深夜まで動画視聴に夢中になる。こんなふうに子どもたちの日常に、多くの問題が生じているのが現状です。反面、特に家庭においてはルールの形骸化、フィルタリング設定や機能制限などの実施率も低いまま。これでは子どもを守れないばかりか、現実的に役立つスマホ教育はむずかしいと言わざるを得ません。
今後、デジタル社会はますます進化し、社会構造も大きく変わると予想されます。チャットGPTに代表される生成AIの普及により、学習の意義や教育の価値も、これまでとは違った意識が持たれるでしょう。まずはおとなが実態を知り、その背景を理解することが大切です。併せて現代の子どもが抱える生きづらさに共感し、おとなが真に子どもの力になれるよう、あらたな視点や心構えを持ってほしいと思います。
本講演では、子どもを取り巻く最新事情を紹介するとともに、今後予想されるAI社会の到来も見据え、実践的かつ効果的なスマホ教育について提案していきます。
3. 自分で考えるネット・スマホ利用
中学生や高校生など、スマホ利用の当事者を対象にした講演会です
NTTなど通信会社主催の講座とは違い、スマホ・ネット利用の具体的なリスクやトラブル対応、いじめの被害回復方法など現実に役立つ情報が満載です。
無料で遊べるオンラインゲーム(スマホゲーム)につい夢中になり、気づいたらやめられなくなってしまうのはなぜだろうか。
YouTubeなどの動画配信アプリで「推し」に投げ銭をしたり、視聴者からチップをもらったりすることに危険性はないだろうか。
LINEのグループトーク内で、誰かを中傷するようなやりとりがつづいてしまうとき、自分はどんな対応をすればいいだろうか。
X(旧ツイッター)やInstagramでよく見かける「モニター登録で半額!」、「お友達紹介で利用料タダ!」などの投稿(DM)には、いったいどんな裏側があるのだろうか。子どもたちが日々利用するゲームや動画アプリ、SNSなどの「あるある事例」を紹介しつつ、「自分はどうすればいいのか」を考えるための内容です。
実際のSNSのやりとりを生徒(児童)と講師で再現しながら対応方法を探したり、ゲームや動画アプリの背後にある「心理的誘導」、「ビジネス戦略」などについて考える機会を設けています。
日頃、何気なく使っているネットやスマホが、場合によっては自分の人生を台無しにするかもしれない、そんな危機意識を持たせ、判断力や想像力、思考力を養うことを目指します。
【ヤングケアラー・ビジネスケアラー・介護】
1. ヤングケアラー ~「家族を背負う」子どもたちの現状と課題
人権擁護・地域福祉・行政関係者研修・一般市民向け講座向け
病気や障害を持つ家族のために、家事や介護、見守りや付き添い、幼いきょうだいの世話などをする子ども・若者を「ヤングケアラー」と言います。
厚生労働省と文部科学省の実態調査(2021年)では、中学生の約17人に1人(5.7%)、高校生の約24人に1人(4.1%)が、「世話をしている家族がいる」と回答。1日のうち家事や介護などのケアに要する平均時間(平日)は、中学生で4時間、高校生で3.8時間に及んでいます。
一方で、こうした生活実態を「誰にも相談した経験がない」という中高校生は6割以上と、学齢期の子どもが支援に結びつかないまま、ひとりで家族を背負っている現状が浮かび上がります。
病気や障害を抱える保護者が就労できないと経済困窮に陥りやすく、場合によっては子どもが暴力・虐待被害を受けることもあります。「家族のケア」という負担のみならず、経済、身体、心理、社会的な問題が複合的に生じているケースも少なくありません。
私自身、二人の甥(実兄の息子)が、かつて「ヤングケアラー」でした。実兄は40代でALS(筋萎縮性側索硬化症)という難病を発症し、当時高校生だった甥たちが介護を担うことになったのです。
当事者の苦悩を身近に見てきた者として、また長年にわたり家族問題を取材してきたジャーナリストの立場からも「ヤングケアラー」の実態を報告し、今後の社会的課題や解決策について皆様とともに考えたいと思います。
2. 働きながら親を看る~ビジネスケアラーと介護問題
企業向き社員研修、地域福祉、市民向け講座など
3. 在宅介護、在宅看取りをするために大切なこと~超高齢化日本の現状と行く末
地域福祉、行政関係者研修、市民向け講座など
国民の約3割が65歳以上の高齢者という超高齢化社会の日本において、「老い」や「介護」の問題は避けては通れない社会的テーマです。一方で、特別養護老人ホームなど公的な高齢者向け施設の入所基準は厳しく、多くの地域で「入所待ち」や「介護人材不足」などの問題が生じています。
2025年には団塊世代がすべて後期高齢者となり、医療や介護需要がますます増大する「2025年問題」も予想される中、国は「地域包括ケアシステム」として、在宅介護や在宅医療を推進する方針を打ち出しています。要は、施設を抑制し、「家で介護を受ける、家で亡くなる」ことが推進されるわけです。
住み慣れた家で高齢期を過ごすのは、多くの人にとって幸せと感じられることでしょう。けれども実際に介護が必要になったとき、誰が介護を担い、日々の生活をサポートするのかという現実的な視点も必要です。
核家族化や夫婦共働きが常態化した現在では、家庭の中に介護を担える人がいないことが珍しくありません。高齢者の単身世帯も増えており、子どもは遠く離れて住んでいるというケースも数多くあります。
仕事と親の介護を両立せざるを得ないビジネスケアラー、離れて住む親をサポートするための遠距離介護など、介護は高齢者だけの問題ではなく、むしろ現役世代にとって極めて大きな課題と言えるのです。
私自身、多忙な仕事を持ちながら、ビジネスケアラーとして離れて住む父を3年間にわたり遠距離介護しました。「病院や施設はイヤだ」、「住み慣れた家で死にたい」という父の願いを叶えるため奔走し、現実の厳しさに葛藤しながら、父の最期に立ち会いました。
同時に、この国の終末期医療や介護保険制度の問題点を痛感し、また、真に必要な、役立つ情報を周知する必要性も感じています。
働きながら親を看るためにどうすればいいのか、リアルな在宅介護とはどんなものか、家族も当人も本当に幸せになれる看取りとは何か、超高齢化が進む今だからこそ、ご一緒に考えていきましょう。
【児童虐待・子どもの貧困】
1. 孤立と虐待のない街づくり~傷つく子どもを支えるためにできること
人権擁護・地域福祉・行政関係者研修・民生委員児童委員研修、市民向け講座
少子化が進行する一方で、全国の児童相談所が対応する児童虐待件数は約22万件(2022年度)と過去最多を更新しています。
殴る、蹴るなどの身体的虐待だけでなく、子どもの前で生じる夫婦間暴力による心理的虐待(面前DV)、劣悪な生活環境に置くネグレクト(養育放棄)も増加。しています。
児童虐待=「子どもがひどい目に遭っている」、そんなイメージを持たれやすいですが、実際にはおとなになってからもさまざまな問題が継続し、被害者の一生に深刻なダメージを与える場合も少なくありません。
安心して過ごせる居場所がない、親を頼れない、不安や恐怖が常態化している、そうした子どもにとって「助けを求められる場所」が、ネット(SNS)に集中しているのも現代の特徴です。
近隣関係が希薄化し、特に都会では地域住民が気軽に子育て家庭に関わることがむずかしくなっています。親の孤立化が加速し、情報化がもたらす「子育て比較」などもプレッシャーになり、子どもに対する怒りや苛立ちを招いています。
「隣の家で何が起きているのかわからない」、「まわりに虐待被害を受けている子どもがいても関わりにくい」、そんな状況下で、私たちには何ができるでしょうか。
子育てを取り巻く環境が激変する今、具体的にどうすればいいのか、まずは現状を認識しましょう。さらに、行政主導の子育て支援や虐待防止対策だけでなく、私たち一人ひとりにできる取り組みを考えるために、各地の最新事例などを紹介。子どもの命を守り、親子の生活を支えるための具体的な情報提供をしていきます。
2. 子どもたちの見えざる貧困~ネット社会で潜在化、深刻化する現状について
人権擁護・地域福祉・行政関係者研修・民生委員児童委員研修、市民向け講座
子どもの7人に1人が貧困状態にあると報告され、近年、「子どもの貧困」は大きな社会問題として注目を集めています。
一方で「いかにも貧しそう」という子ども、たとえばボロボロの服を着ているとか、まともに食事もしていない様子とか、従来の貧困のイメージに合うような子どもは見当たらず、「いったいどこが貧困なのか?」と懐疑的に思う人も少なくありません。
実際、子どもの貧困は外から見えにくく、だからこそ問題が深刻化しやすいという特徴を持っています。
一口に貧困と言っても、経済的な貧困だけではありません。ネグレクト(養育放棄)等による愛情の貧困、親族や近隣、行政などと断絶する関係性の貧困、正しい情報や社会的経験を持たない機会の貧困など、多方面にわたって問題を抱える子どももいます。
また、親の病気(精神疾患など)や障害によって経済的に困窮する家庭では、単なる貧困問題にとどまらず、子どもが親の世話を担いながらも、反面ではその親から虐待されてしまうといった複雑な状況も生じています。
さらにネット社会の今、貧困や家庭崩壊などの問題を抱えた子どもをターゲットにするあらたな問題も急増しています。SNS上で「お金をあげる」、「助けてあげたい」、そんな甘言で子どもを引き寄せ、性的被害を与えたり、犯罪に加担させたり、ビジネスとして利用しようとするのです。
潜在化、そして深刻化する子どもの貧困問題について実態を報告し、具体的な対応策、あらたな取り組みについて考えていきましょう。
3. 親子が笑顔で向き合う子育て
子育て支援、地域福祉、民生委員児童委員研修、市民向け講座
近年、「スマホ育児」という言葉が使われ、育児用のアプリや子育て情報サイトを活用する保護者も増えています。
便利なアプリで子育ての負担が軽減される反面、膨大な情報に翻弄され、かえって追い詰められるようなケースもあります。
たとえばSNSでは、子育てに関する多数の投稿が「比較」につながりがちです。他者の成功や幸せアピールを目にすると、「ウチの子はダメなのでは?」、「私の子育ては大丈夫だろうか?」と不安が高まったりするのです。
一方、子どもの日常にも大きな変化が表れています。幼少期からのインターネット利用により、幼児や小学生がゲーム、動画視聴などに夢中になっています。親子が直接的に触れ合うのではなく、スマホを介してつながるような生活では、子どもの心身の成長にあらたな問題が生じる可能性もあります。
どうしたら親子が笑顔で向き合えるのか、そのためにどんな支援策が必要なのか、複雑化する子育て環境の現状と併せ、真に豊かで幸せな子育てとは何かを考えてみましょう。
著作紹介
ギャラリー
講師紹介動画
聴講者の声
- 今流行っている事の裏にある危険な事など、詳しく、わかりやすく説明してもらい良かった。子どもを信じる形でルールを決めたいと思った。
- 子ども達を取り巻く環境の難しさを感じました。危険な事を教えていくのは勿論のこと、人とのつながりを必要以上に求める心の不安、自信の無さを、家庭や教育現場で解消し、強い心を育てていかなければと思いました。反面、メリットを具体的に知ると、良い時代が来たなぁと嬉しく思いました。
- インターネット(スマホ)について知らないことが、いかにたくさんあるかを気づかされました。また人と人との関わりが大切であることについて、今日私たちが学んだことを、聞いていない人にどう広げるかが課題だと思います。
- ネット依存は怖いと思いました。子どもと一緒にネットについて考えていく必要があると感じました。
- 子どもを育てる力を伸ばすためには、子どもを主体的に考え、行動させるようなことを大人が考えなければ!との思いを強くしました。
- 中、高生の子どもがいるので、これからインターネットと子どもとどう向き合っていったら良いか、とても参考になりました。家庭でのスマホの使い方をもう一度見直します。子どもにも聞かせたかったです。
- SNSに疎い年齢のため、初めて聞く内容も多く、怖さを良く知れた。又、良い使い方も知れてとても勉強になりました。